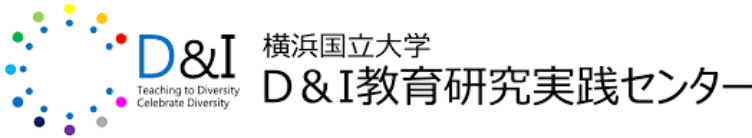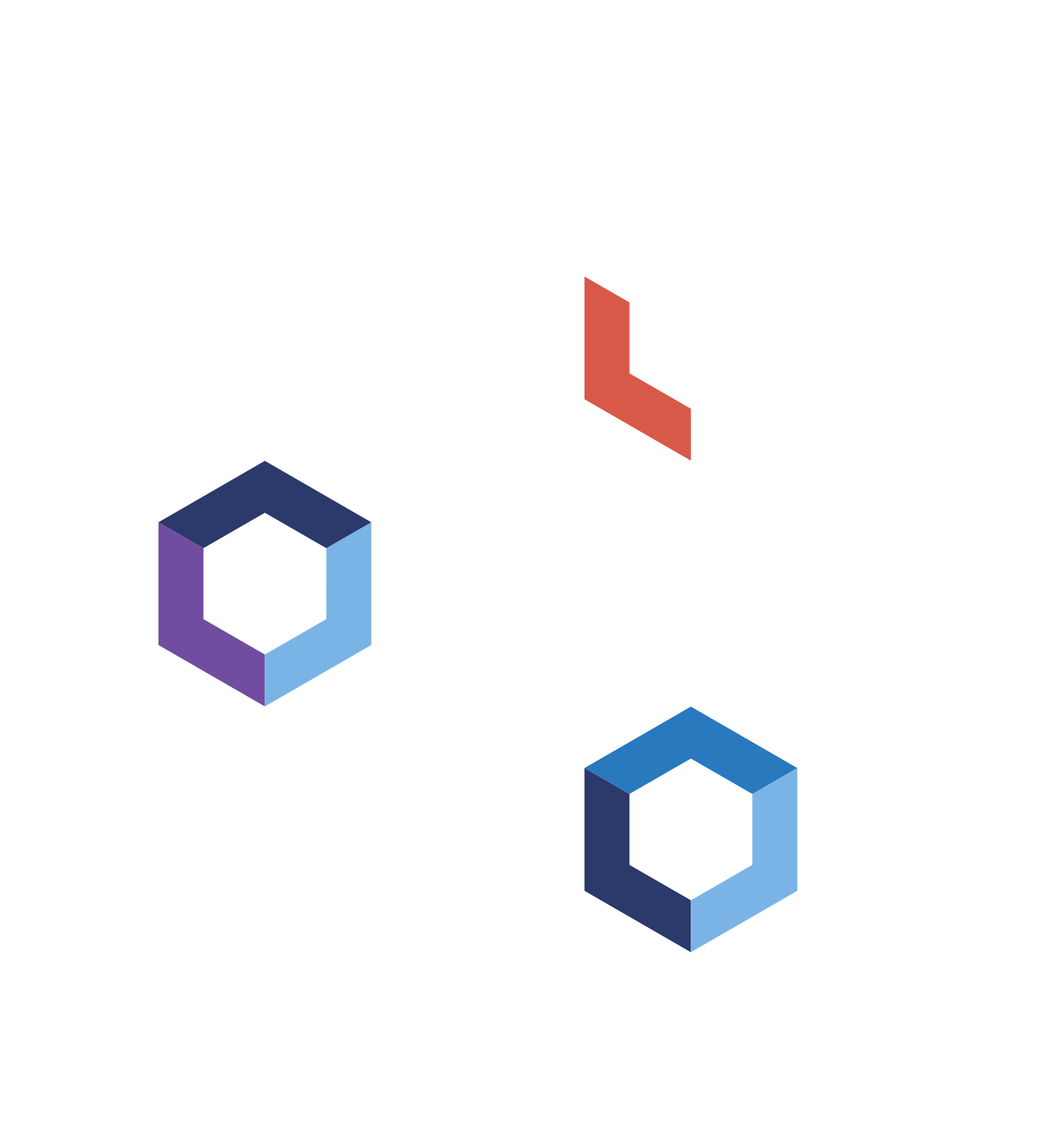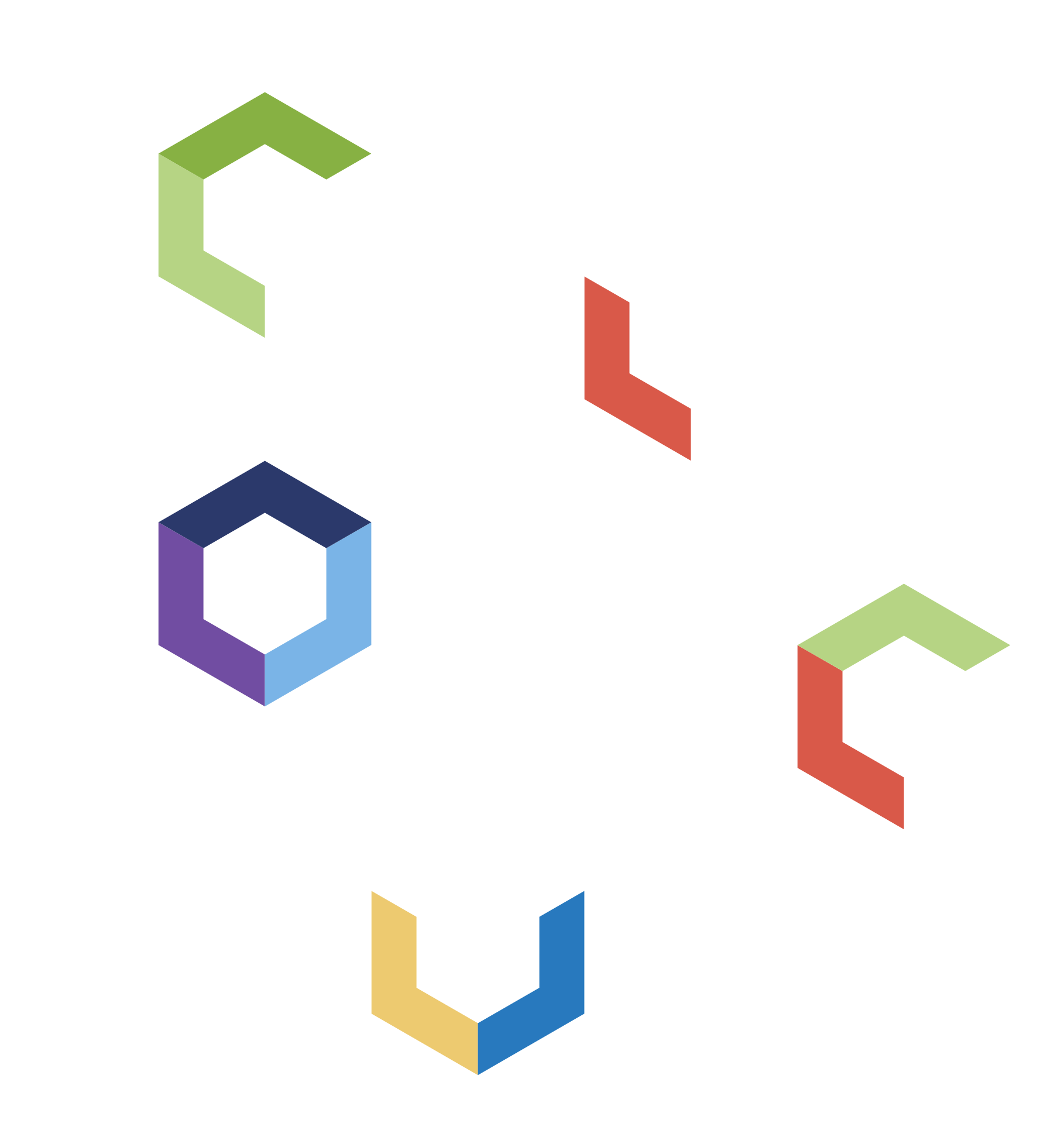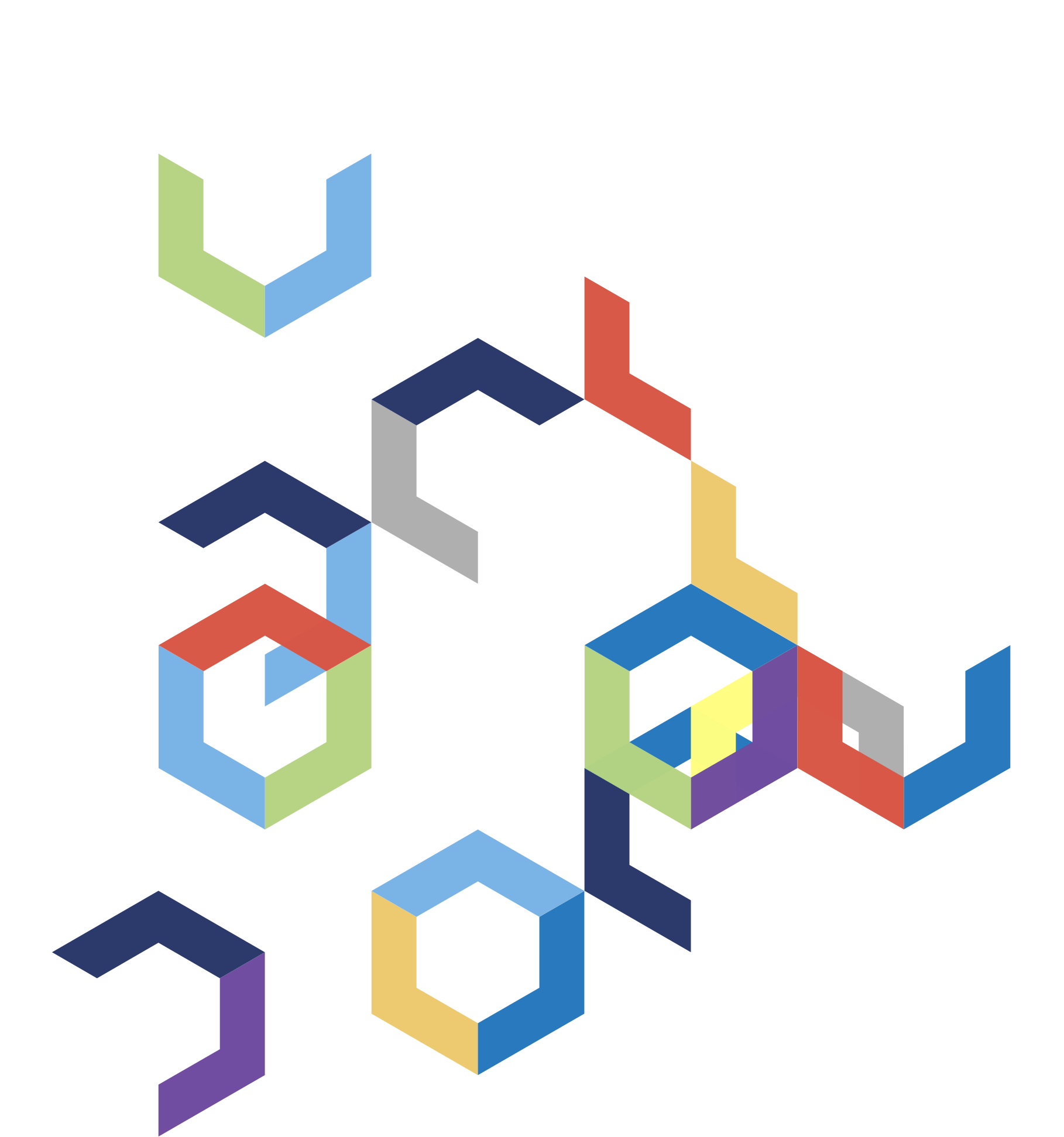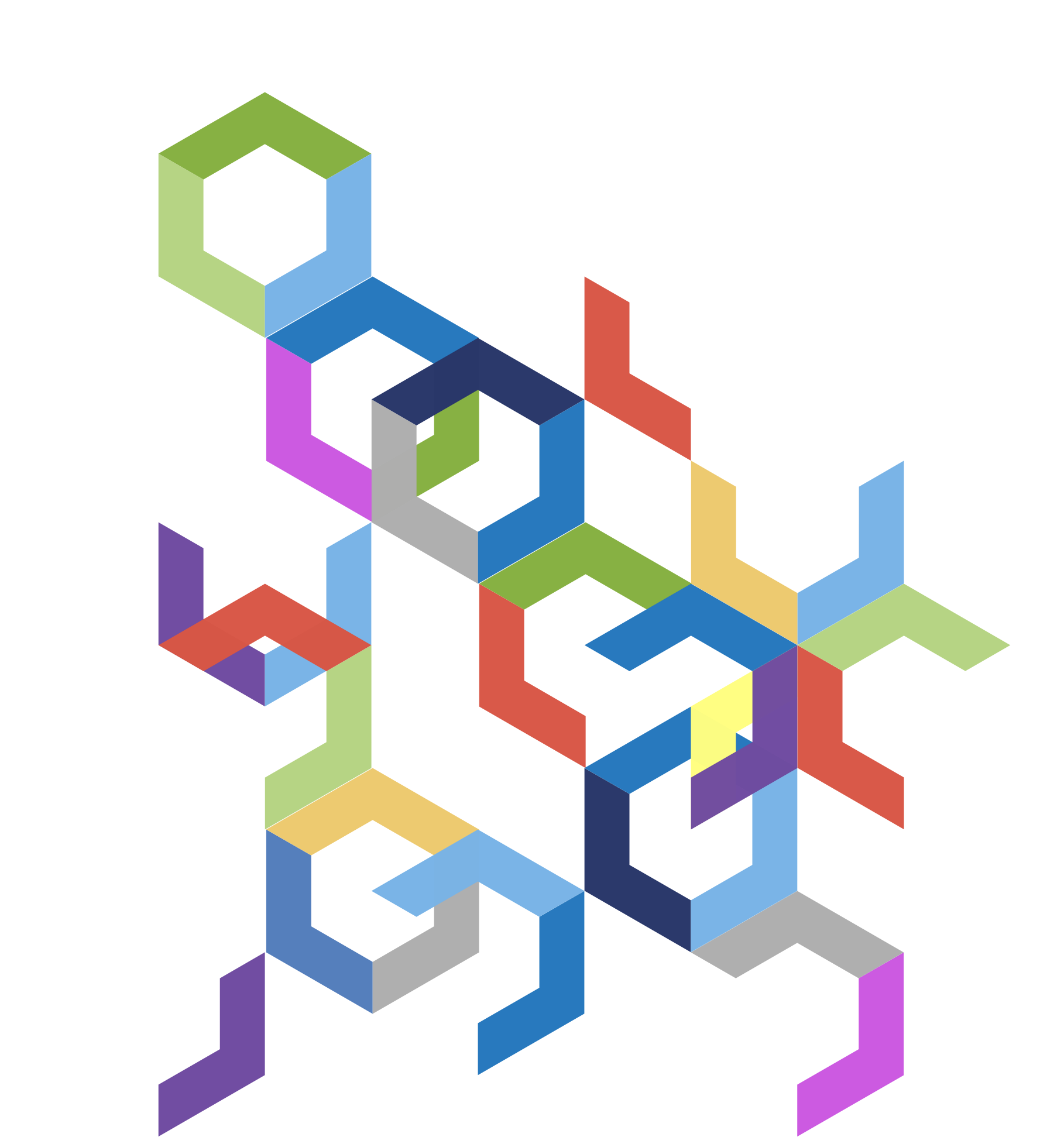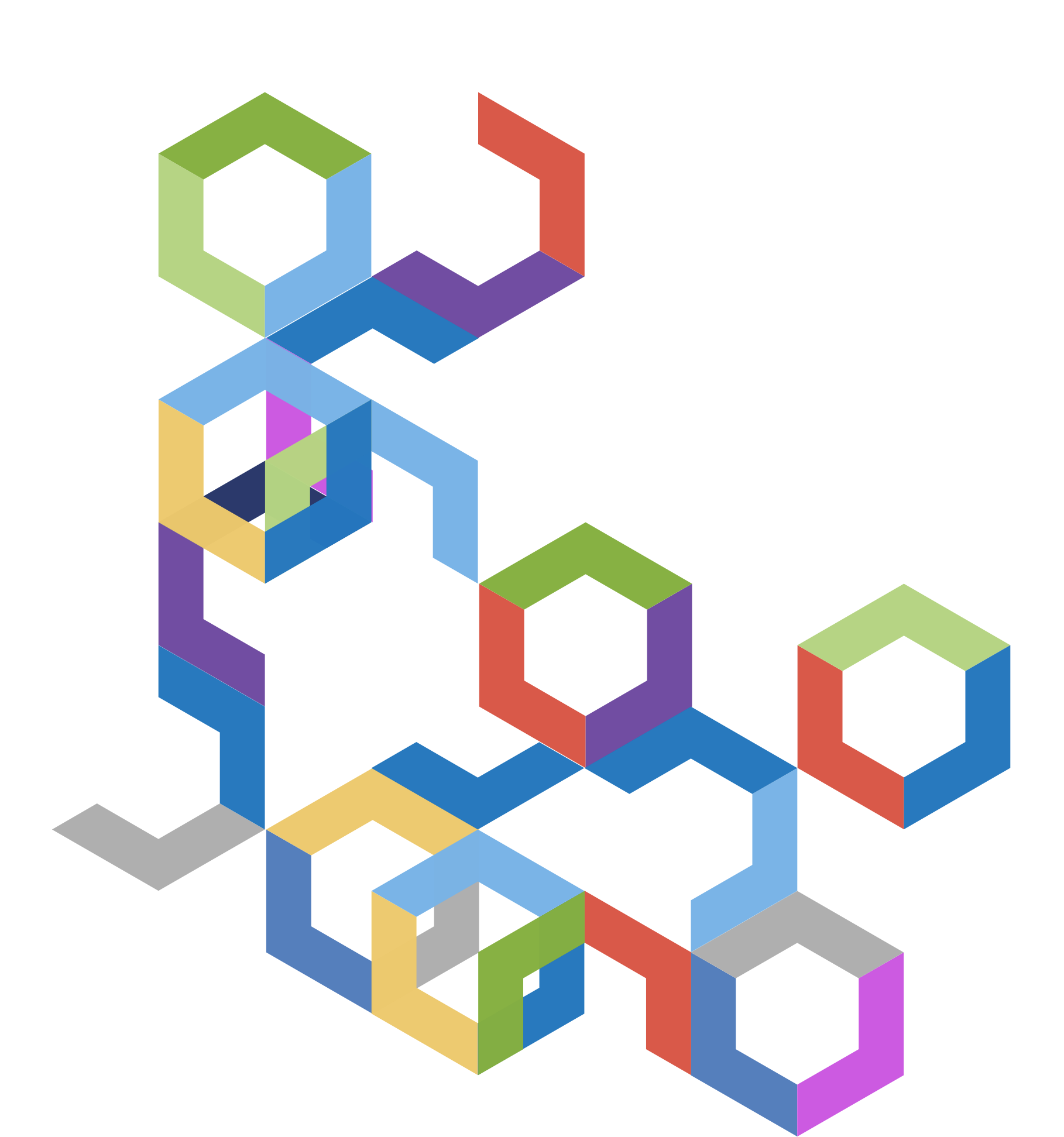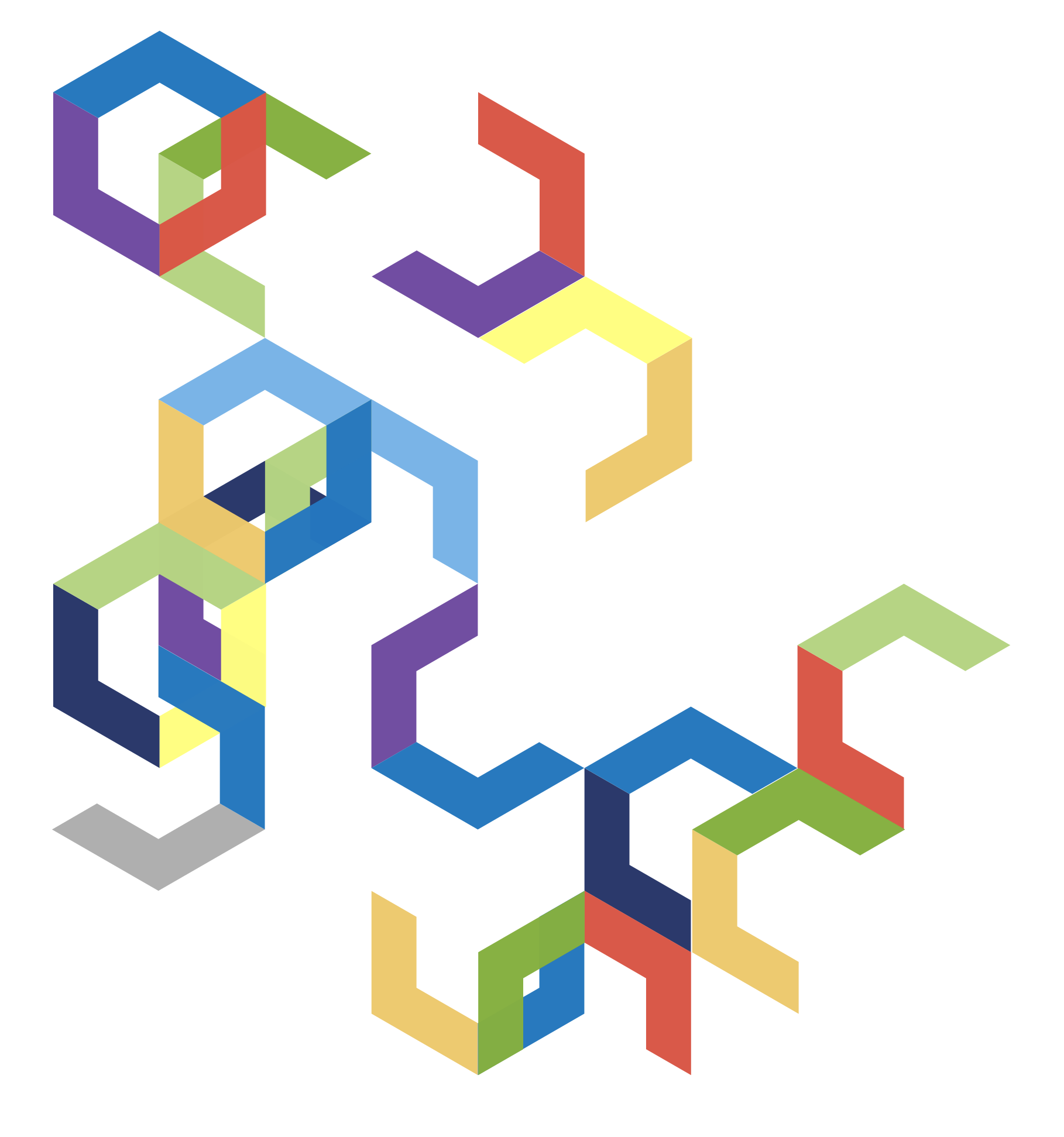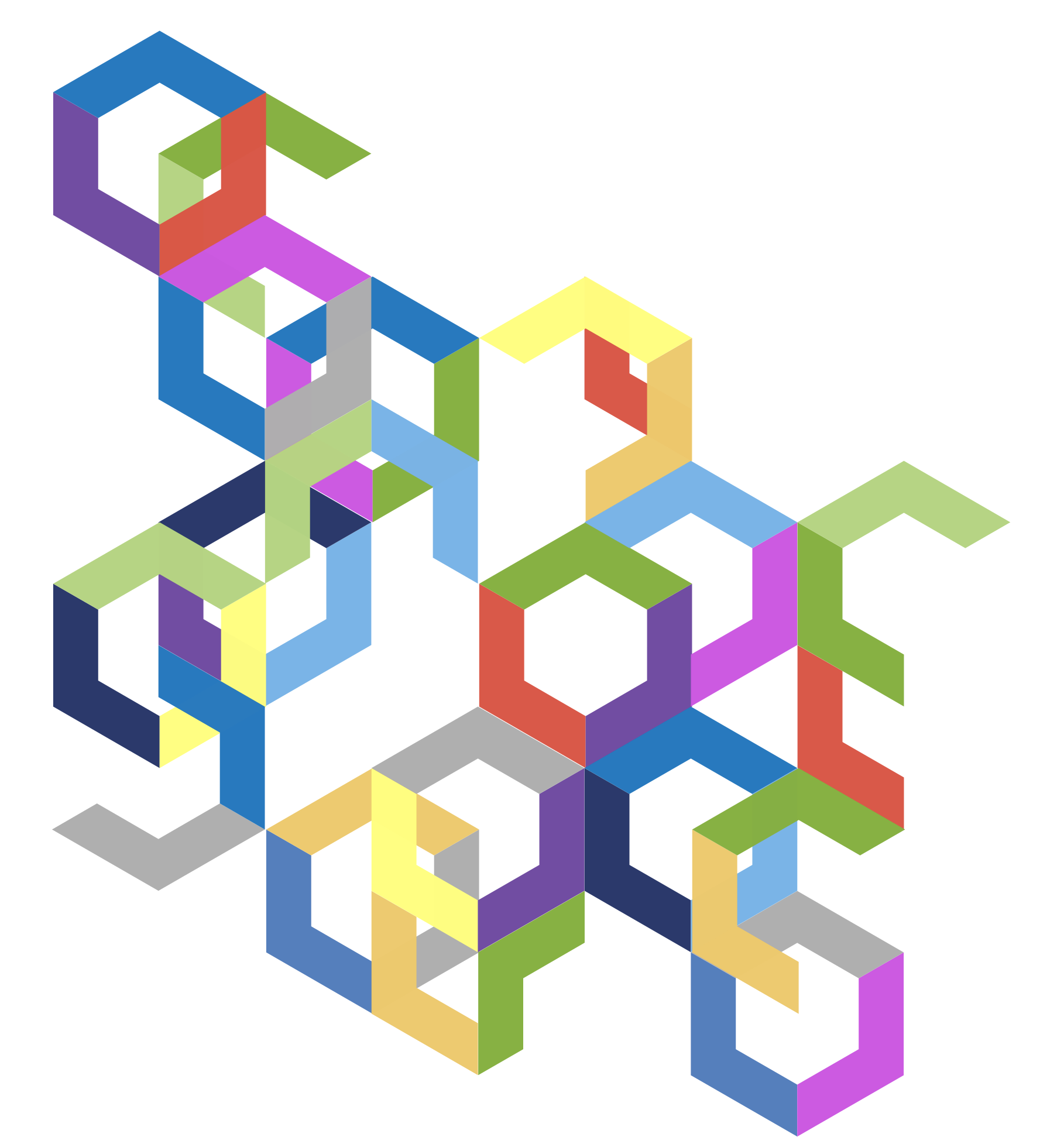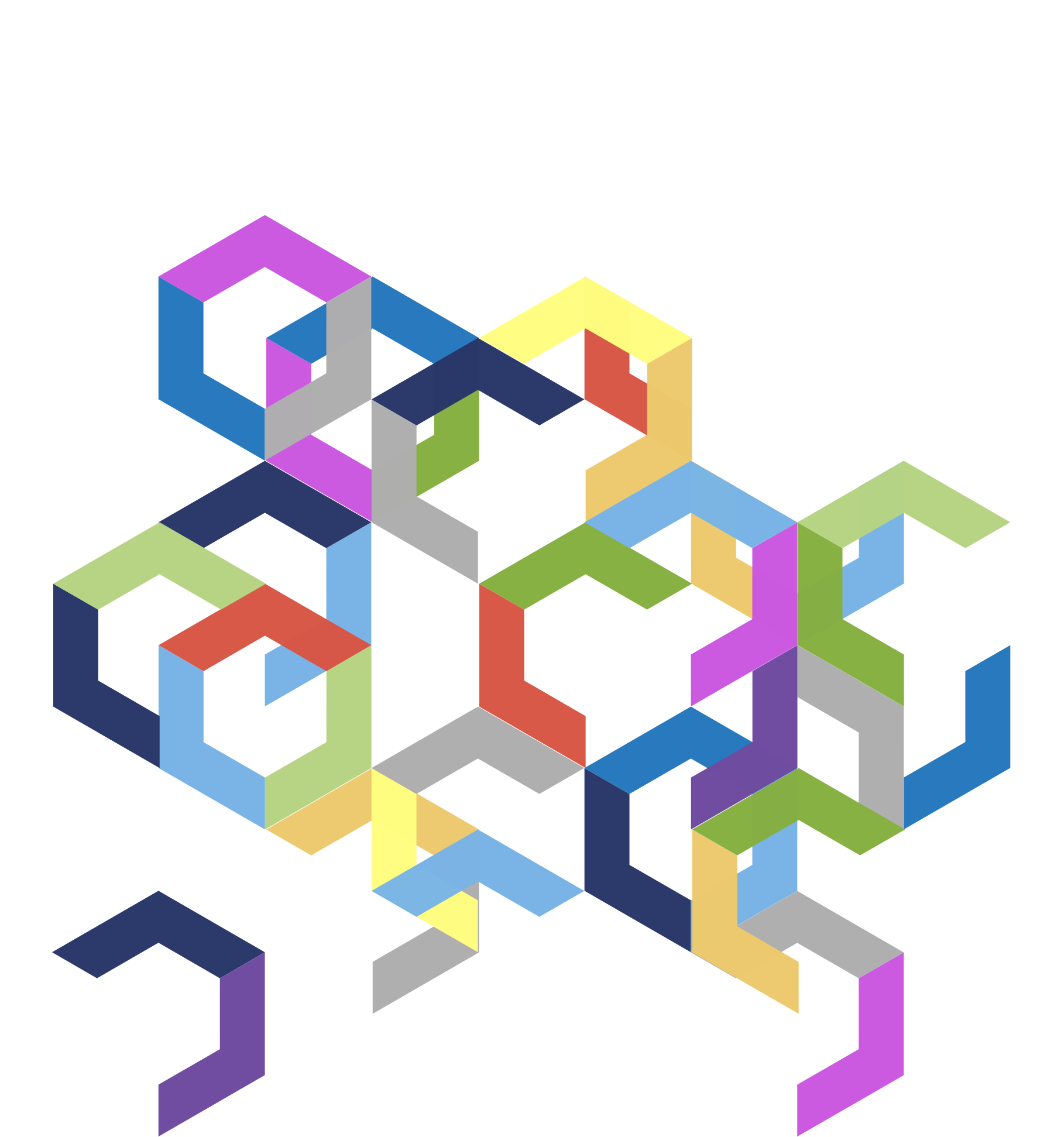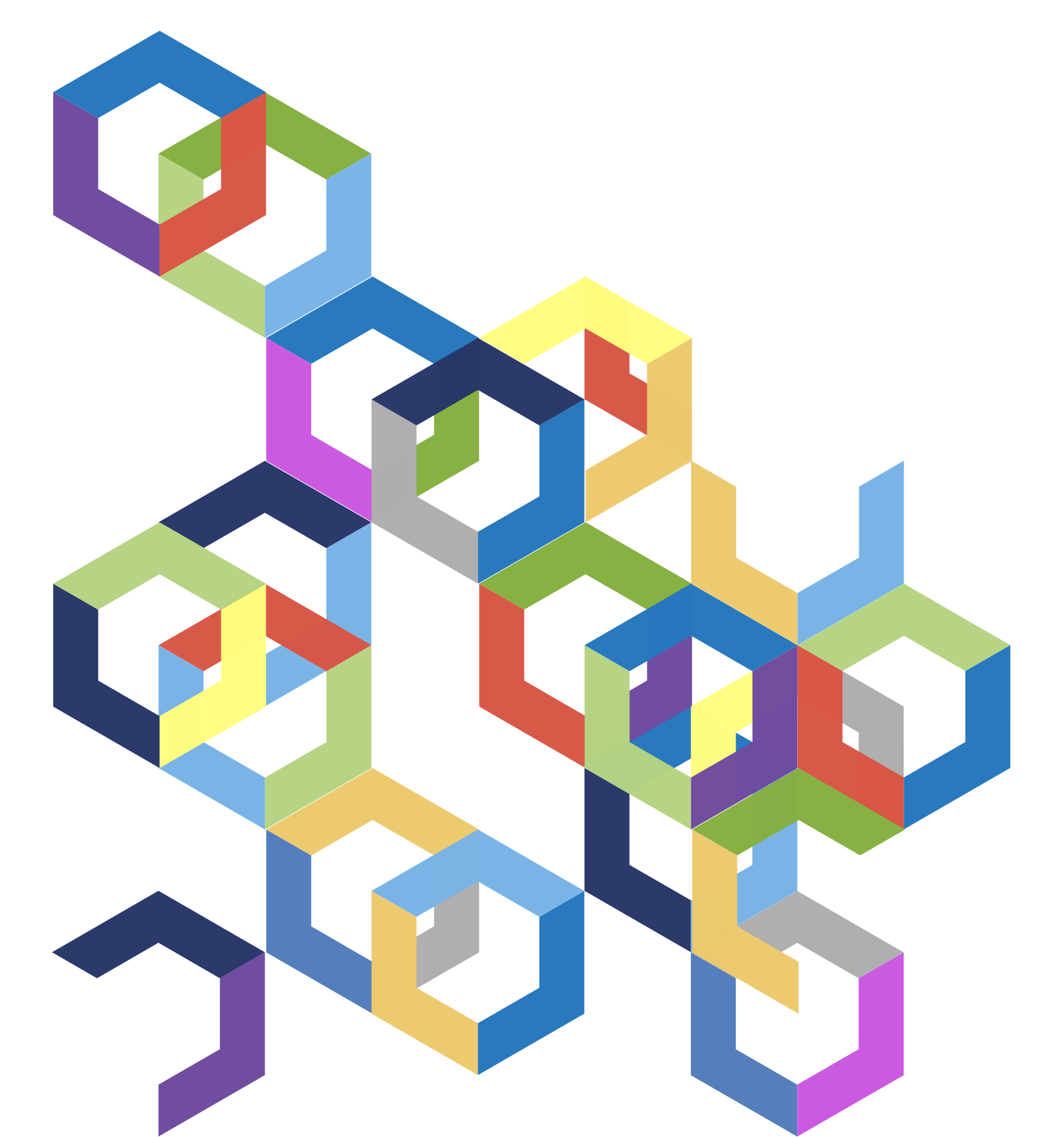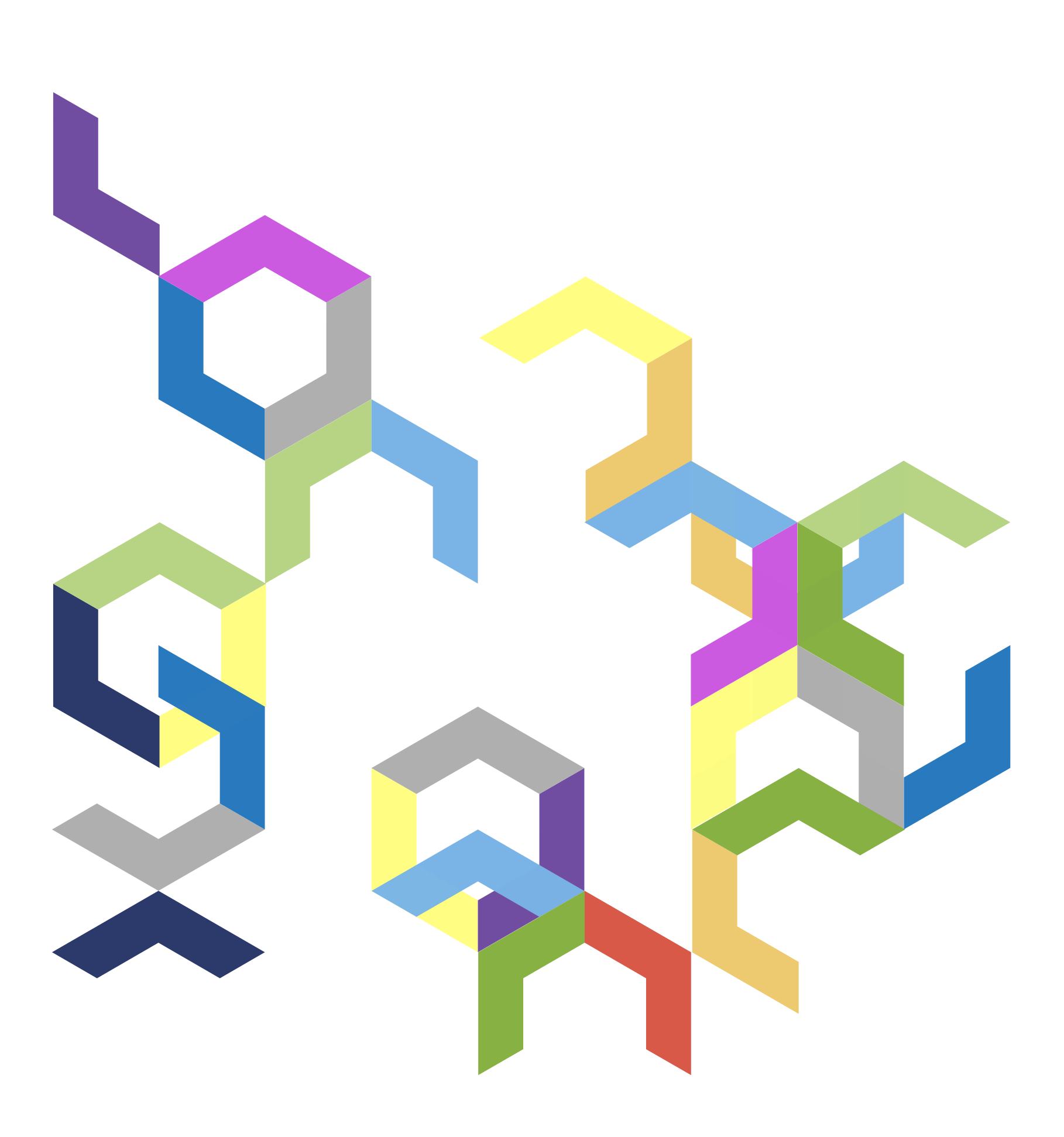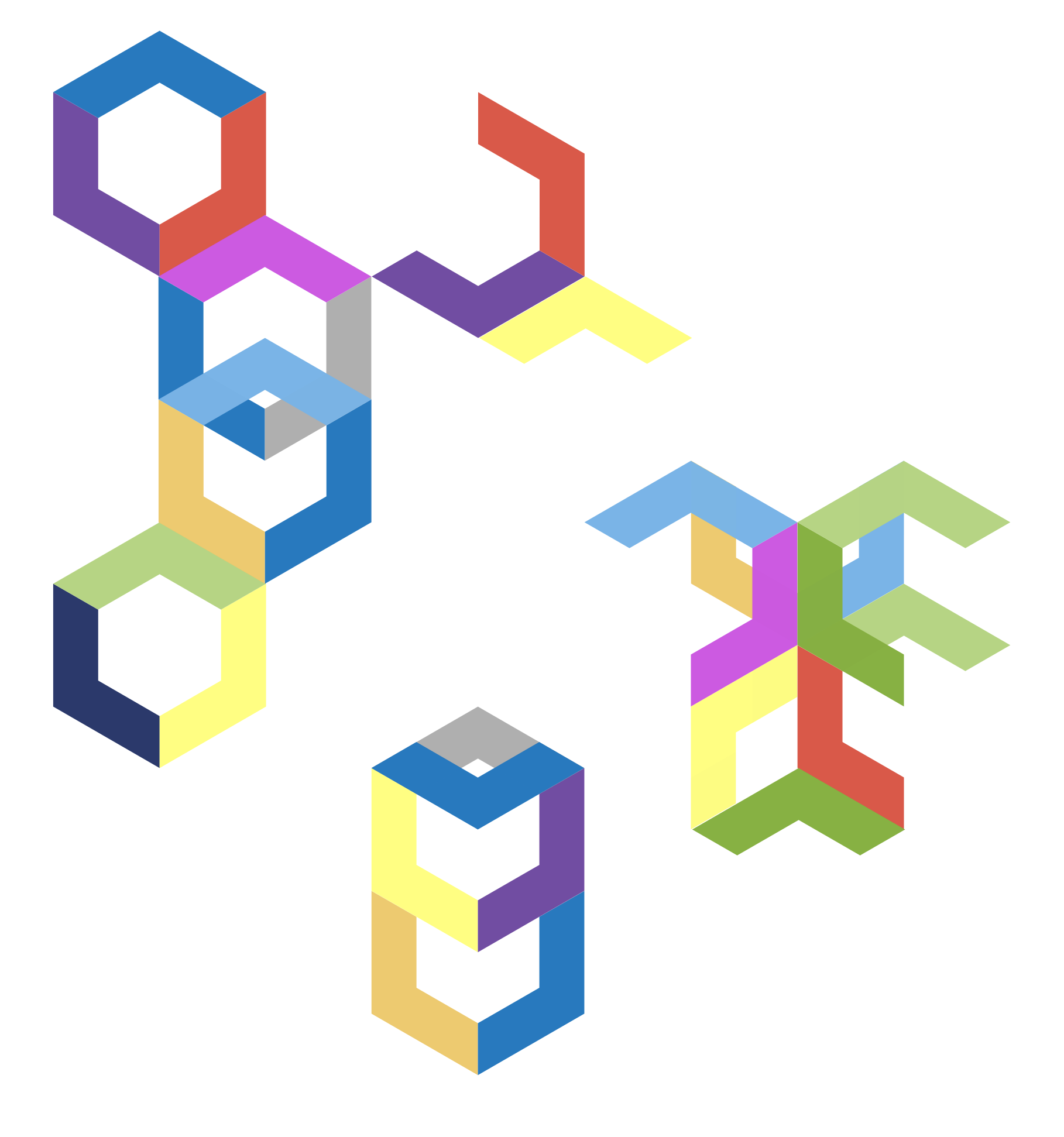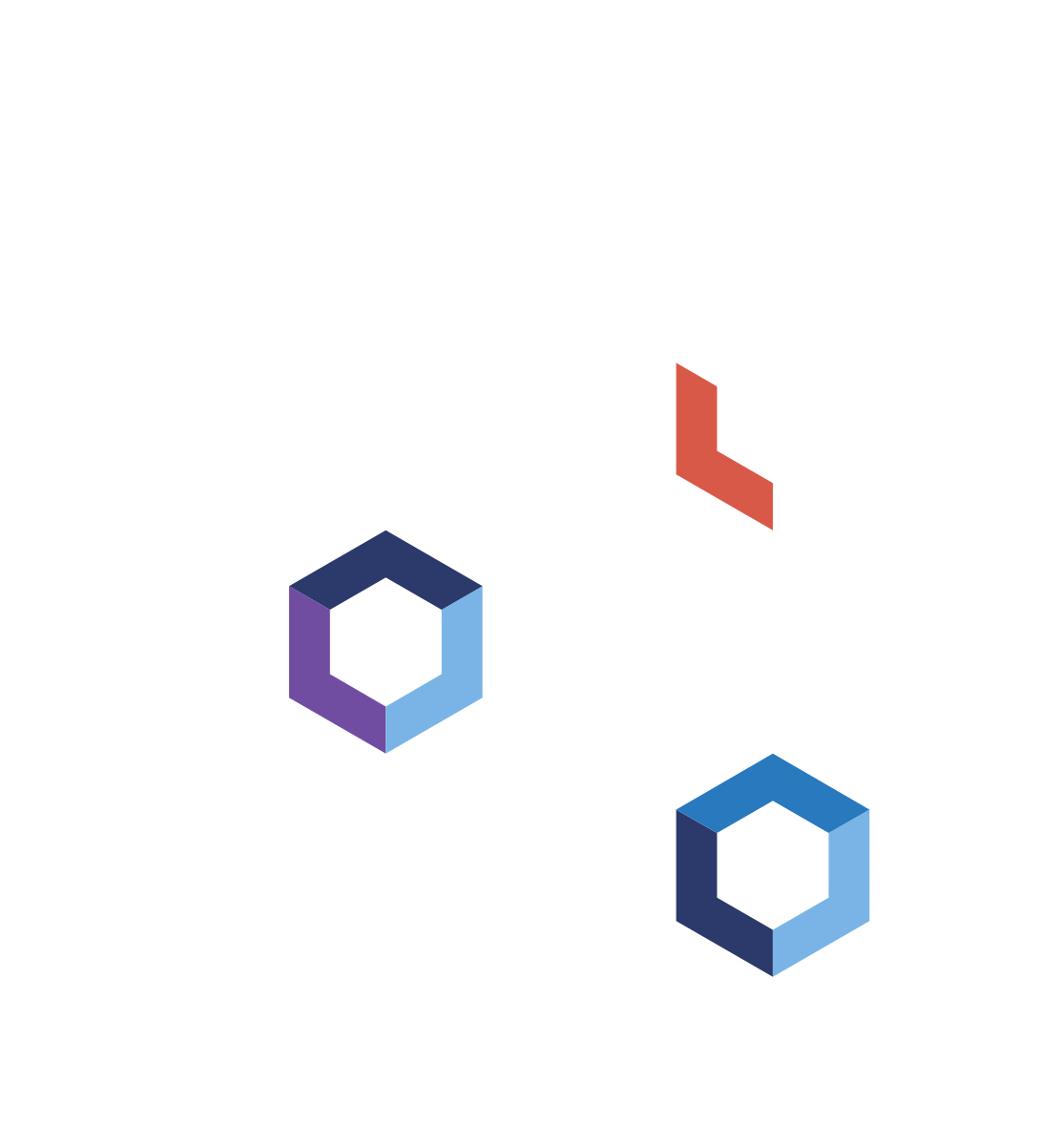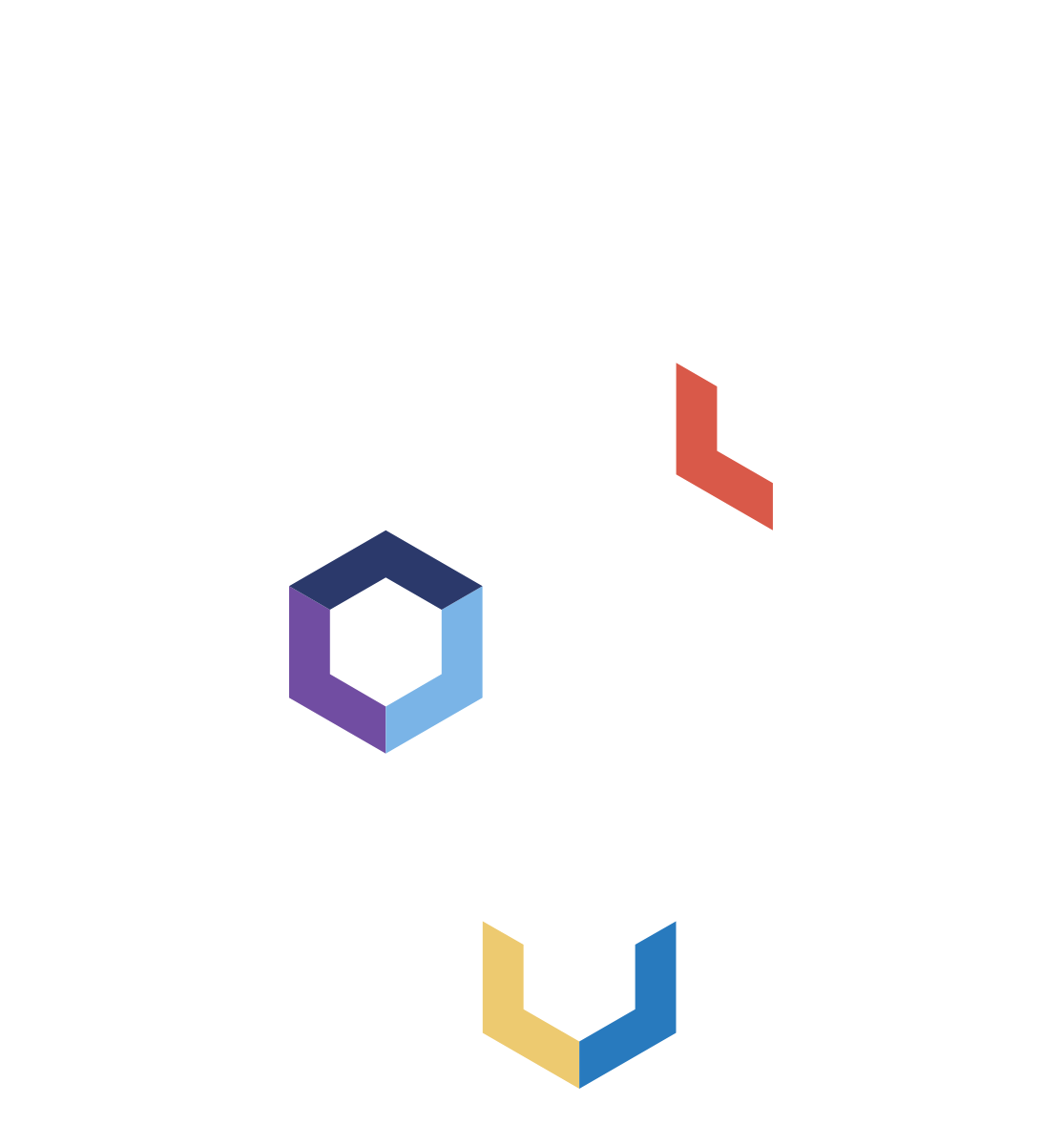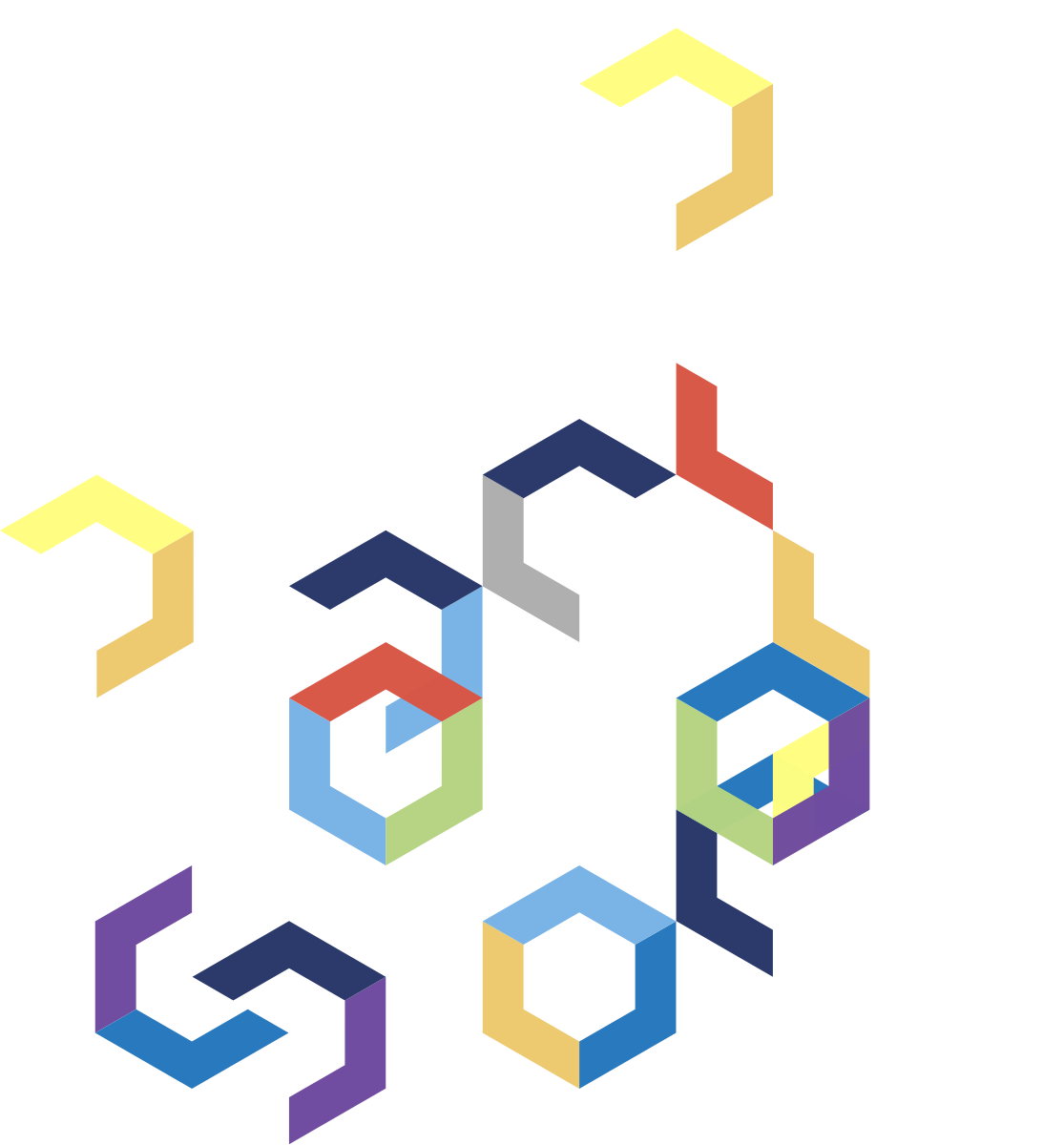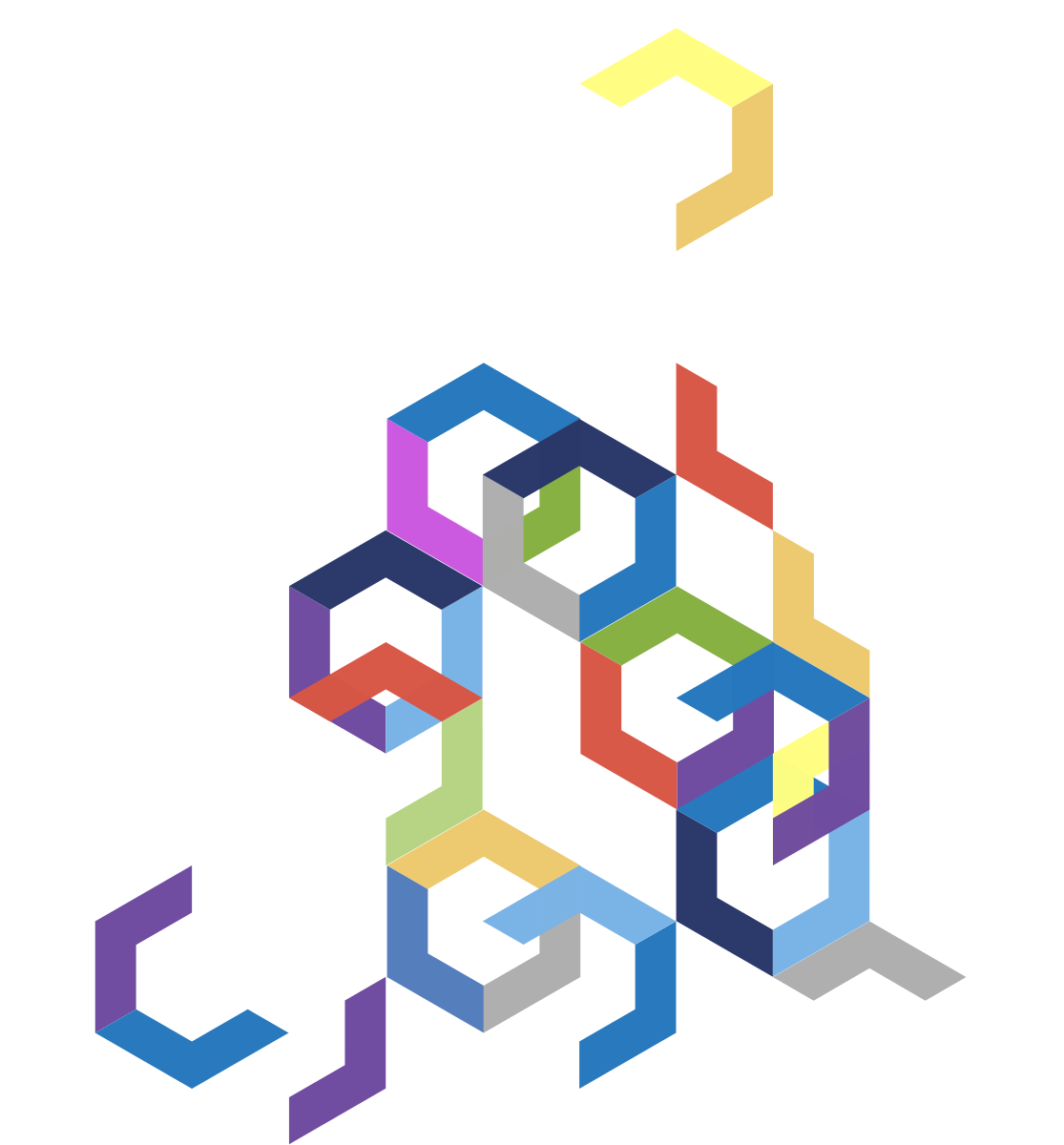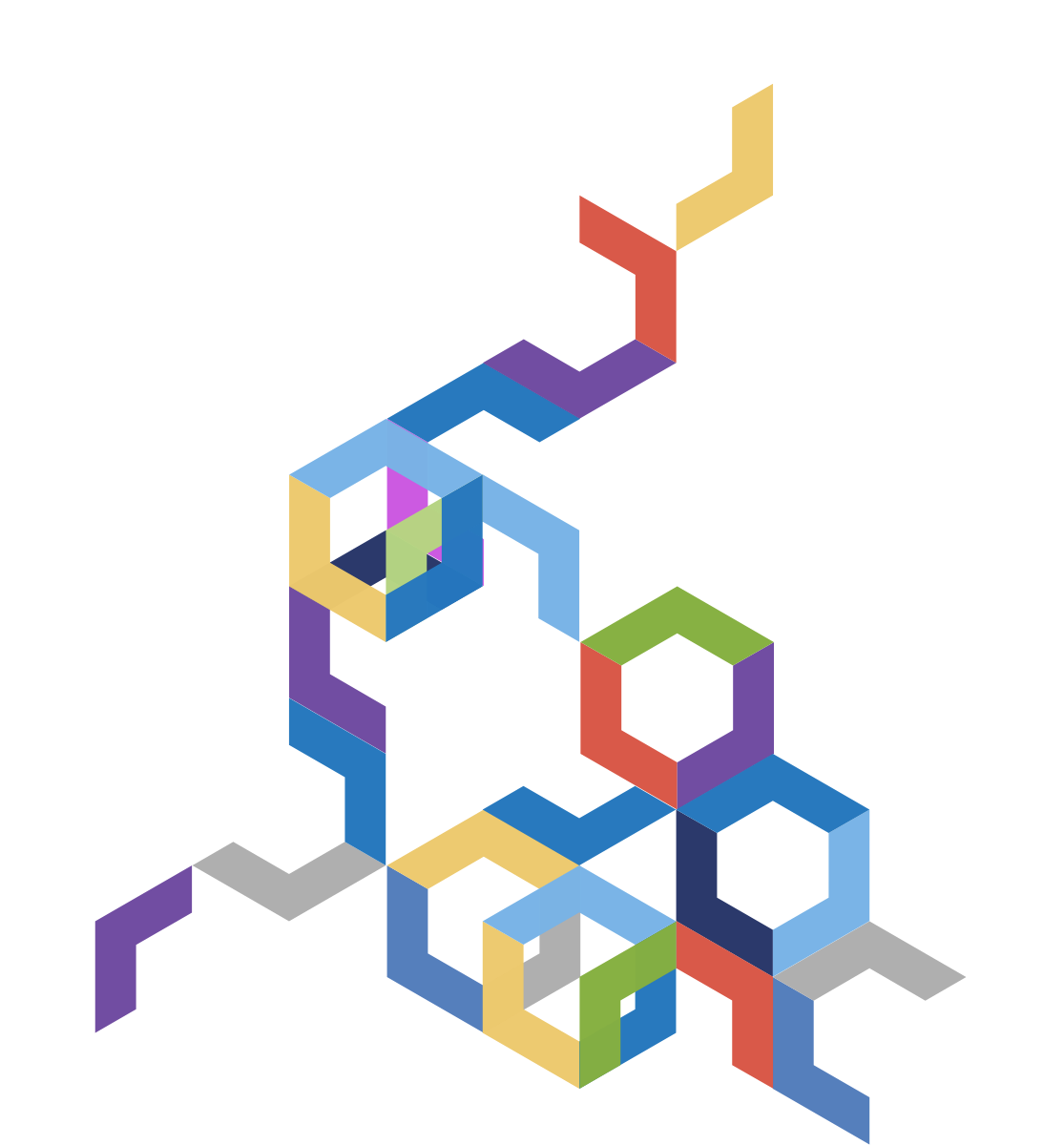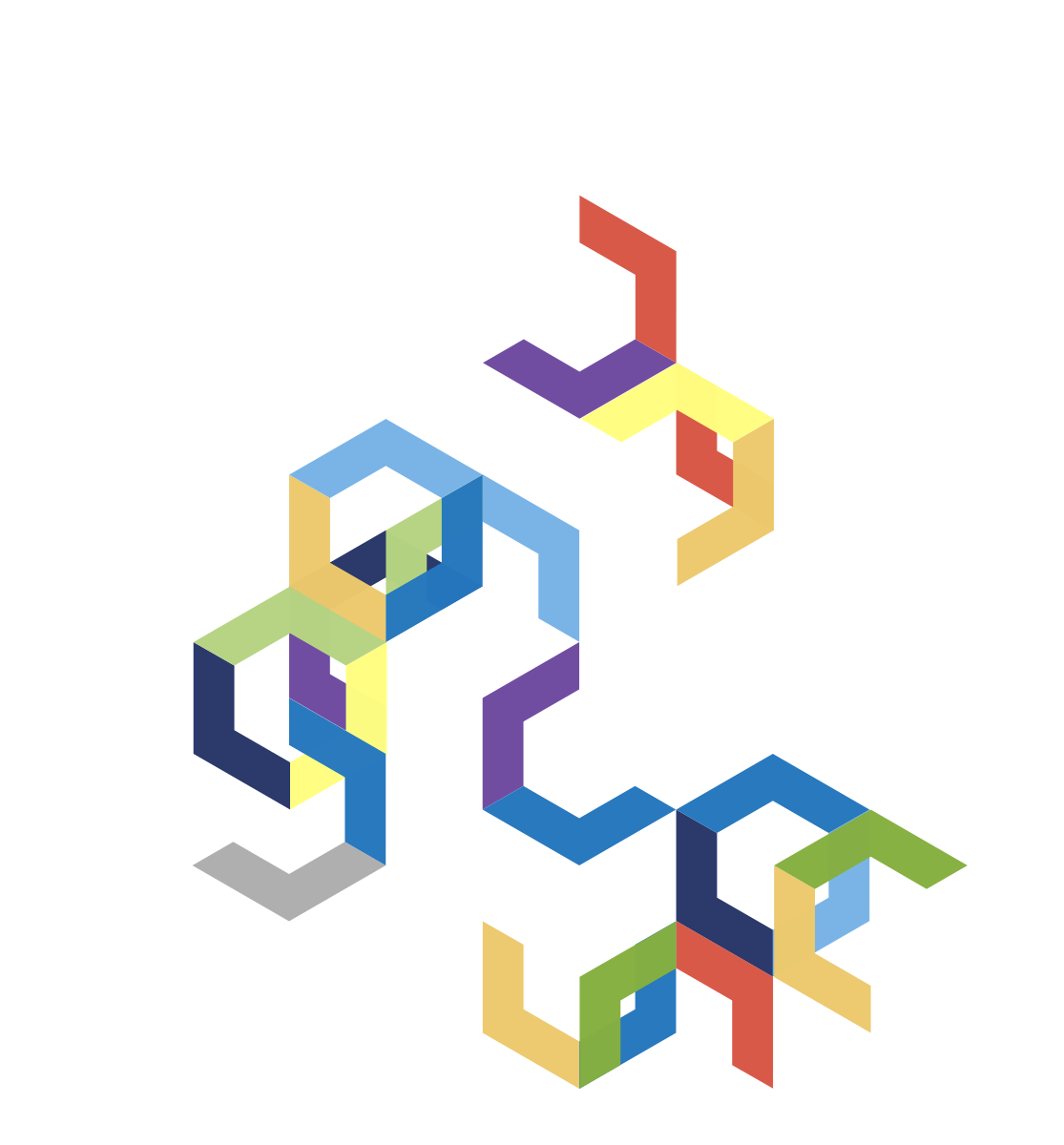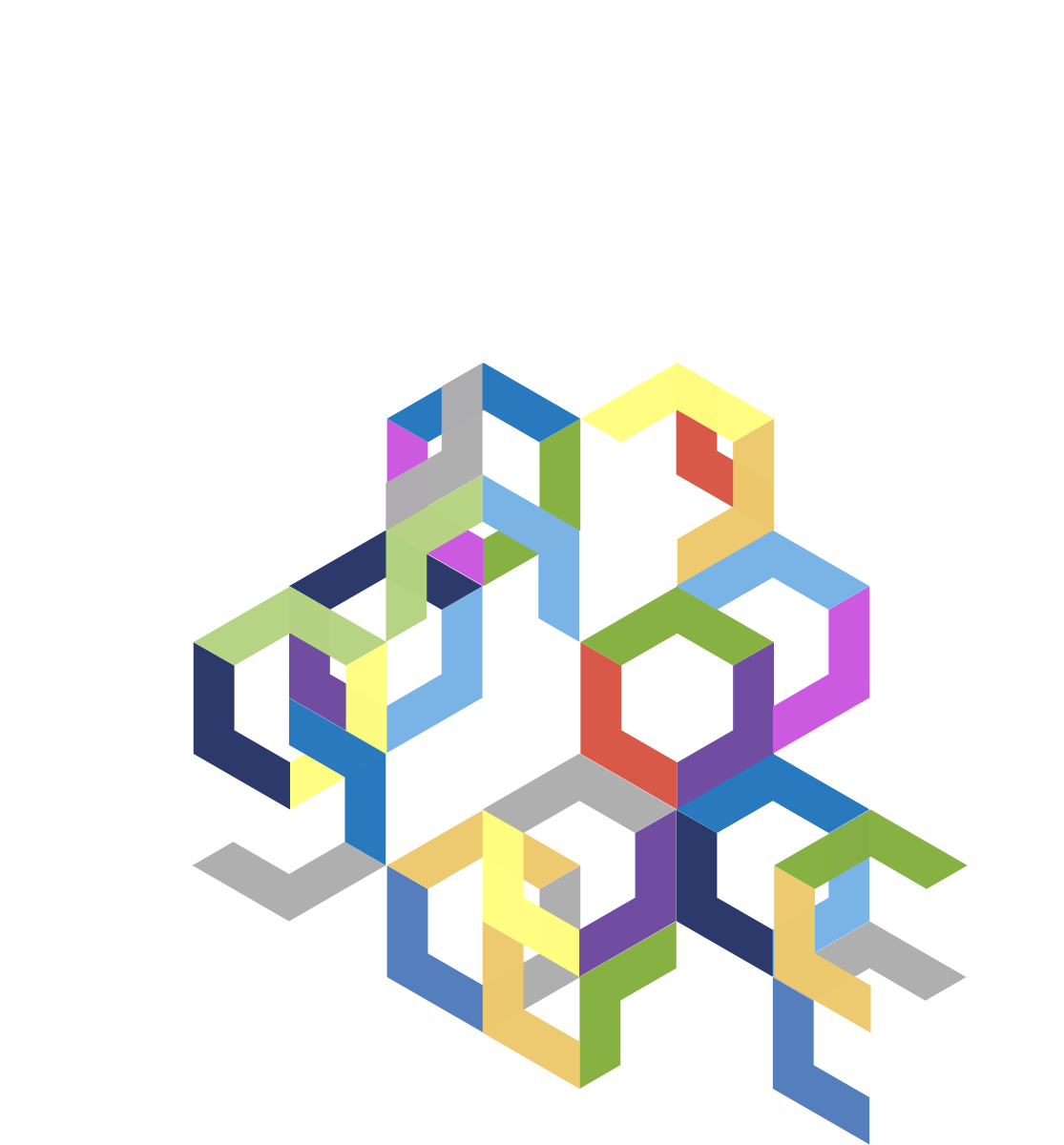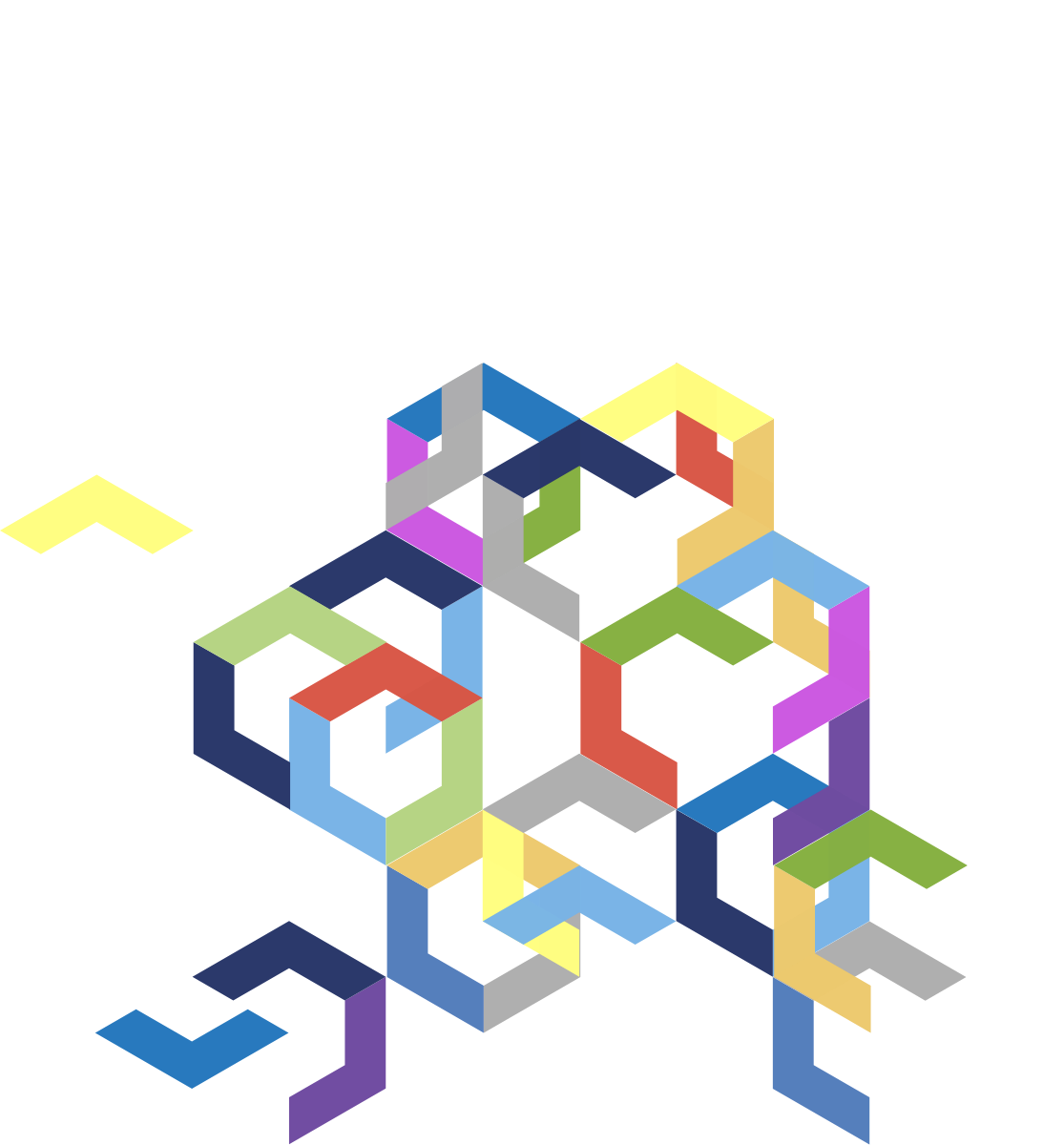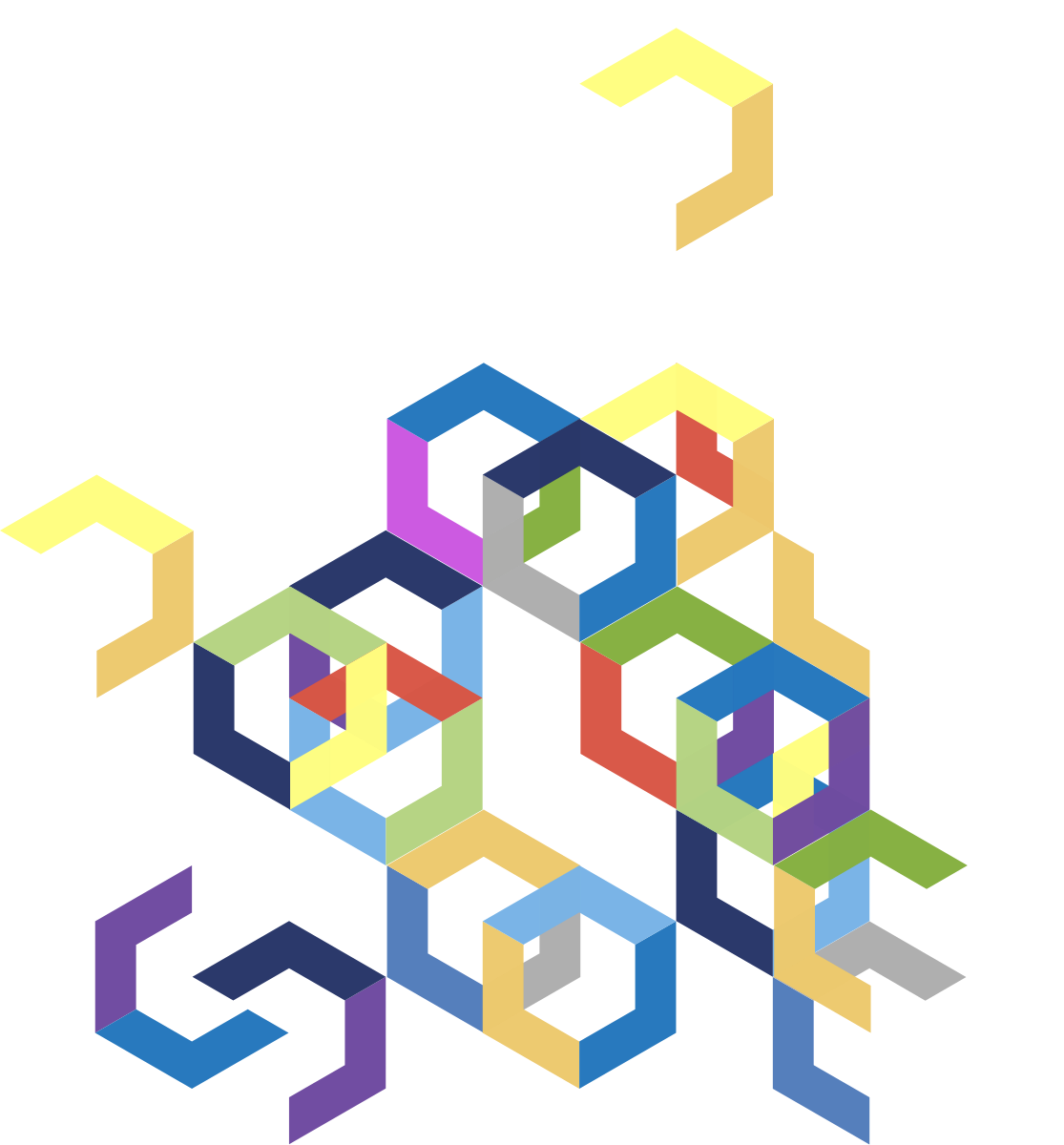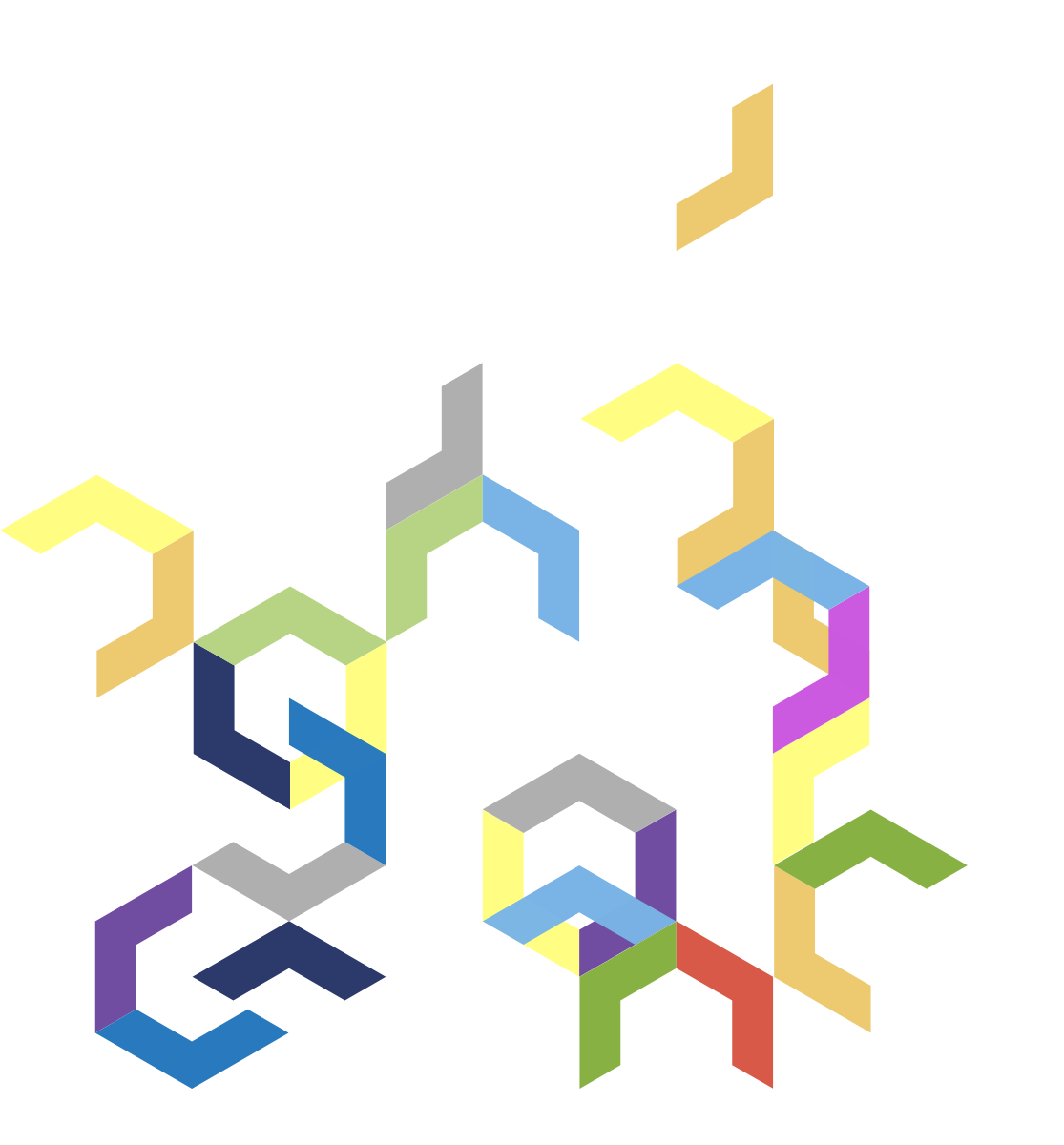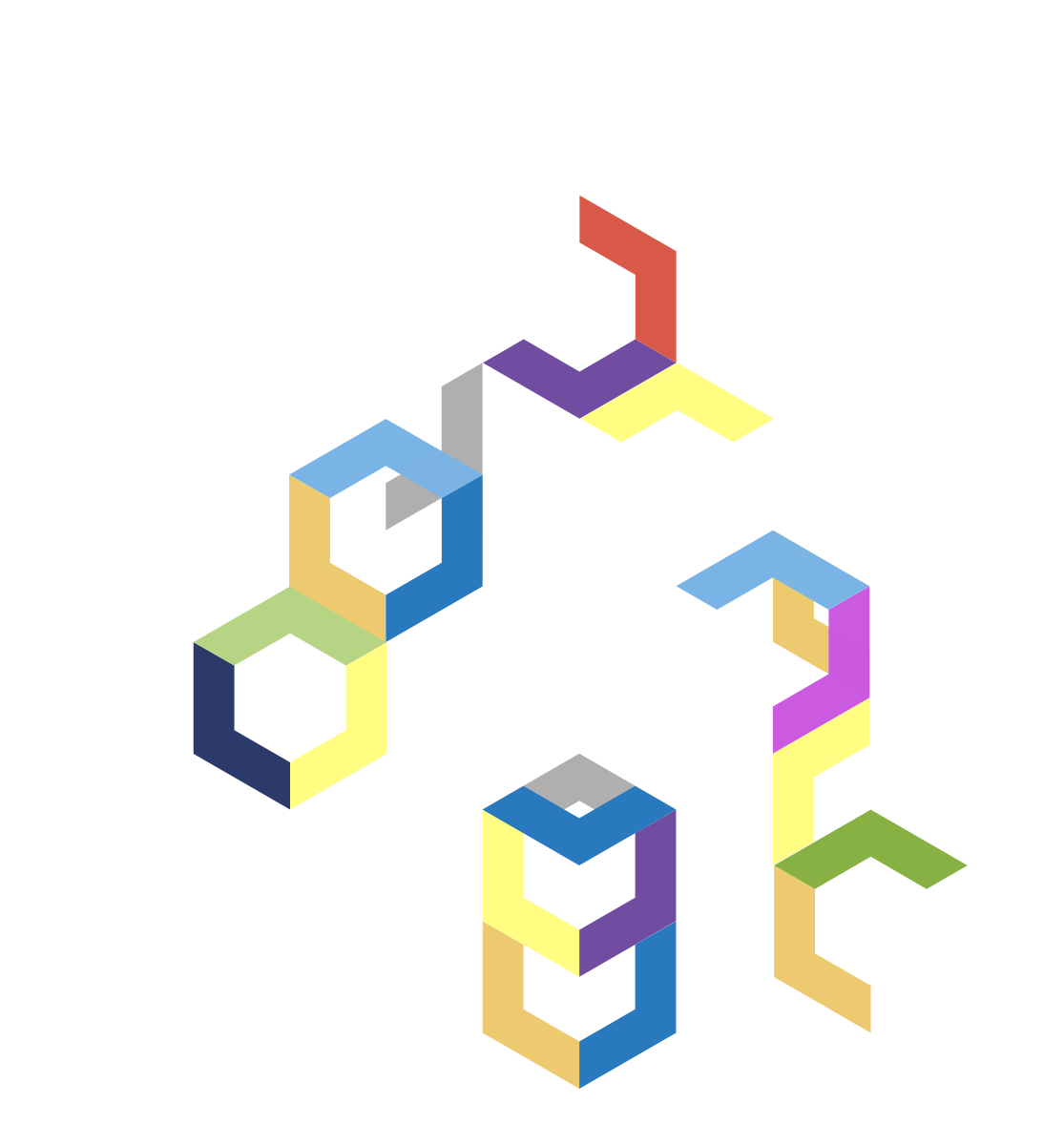ICT機器で「Want=〜したい」を叶える支援〜首から下が自由に動かない生徒への支援実践報告〜vol.1対象者の紹介✨
2025.10.17
皆さんは、日常の中で「Want〜したい」と思ったことを自分で選んで行動に移せていますか?例えば「今日はどこに行こうかな」「このおかずから食べようかな」といった、些細だけれど大切な“自分で決める”という行為は、多くの人にとって当たり前に感じられるかもしれません。
しかし、障害がある方にとっては、自分のWantという気持ちをうまく伝えられなかったり、その意思を周囲に委ねざるを得ない場面が少なくありません。好きな音楽を聴く場面で、「この子はアイドルが好きだからこの曲にしよう」と周囲が判断してしまうこともありますが、もしかしたら本人はその日、ランキング1位の新曲を聴きたかったかもしれません。こうした小さなズレが、少しずつWantを曖昧にしてしまうことがあります。
今回ご紹介するのは、そんなWantを自分の力で実現できるようになった、ある中学生の支援実践報告です。身体の自由が限られていても、「私はこれがしたい」と伝えられる手段を手に入れたことで、日常生活でも学習の場面でも、自己決定の力が育まれていく様子が見えてきました。
少し長くなりますので、vol.を3つに分けて紹介したいと思います!今回はvol.1対象者の紹介です。
✨対象生徒のプロフィール
・脳性麻痺があり、首から下を自由に動かすことが難しい。
・通常の学級に在籍し、日々の授業に参加している。
・ノートの筆記や教科書をめくる際には、支援員や教員によるサポートを受けている。
・生活全般でも、教員や支援員が常時付き添い、必要な介助を行っている。
・発話は可能で、基本的なコミュニケーションを取れるが、筋緊張や痙縮の影響により、言葉が聞き取りにくい場面もある。
・支援実施前は、「〜はできない」と消極的な姿勢を見せることが多かった。
✨本人・保護者の願いから見えた支援の方向性
今回の支援は、「自分の力でやってみたい」という、本人の願いから始まりました。家庭学習や余暇活動で、教科書をめくる、ノートを取る、YouTubeを検索するといった行為も、これまでは支援者の手が必要でした。そんな中、ICT機器の紹介や、音声による操作方法を伝えると、本人は、「わからないことを自分で調べてみたい」「おすすめ以外の動画も、自分で選んで見たい」と具体的な希望を口にし、“できるかもしれない”という感覚が芽生えました。
保護者も、本人の学習意欲を尊重しながらも、日々の仕事や家事に追われ、十分に手をかけることが難しい現実を抱えていました。「塾にも通わせたい気持ちはあるけれど、受け入れ先が見つからない」「自分でできることが少しでも増えたら、本人にとっても、家族にとっても大きな力になるはず」と切実な思いが語られていました。
こうした本人と保護者の願いを受け、「ICT機器を活用し、本人が自らの力で学ぶ・調べる・記録する体験を積み重ねること」を支援の核に据えました。単なる情報提供ではなく「自分で選ぶ」「自分で決める」「できた!」を実感できる仕組みづくり、それが出発点です。