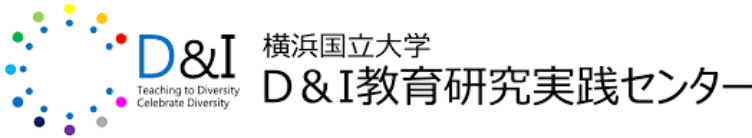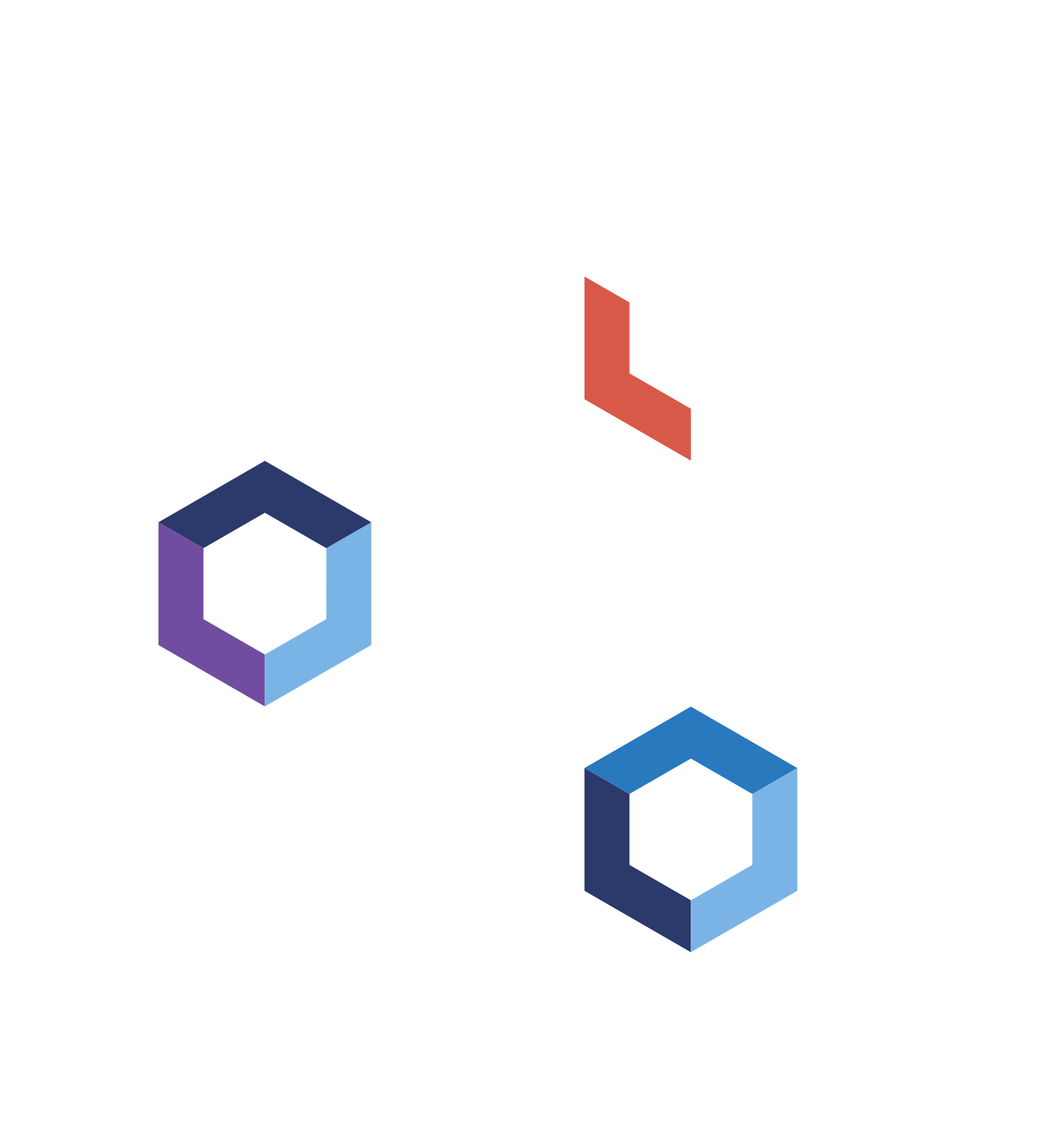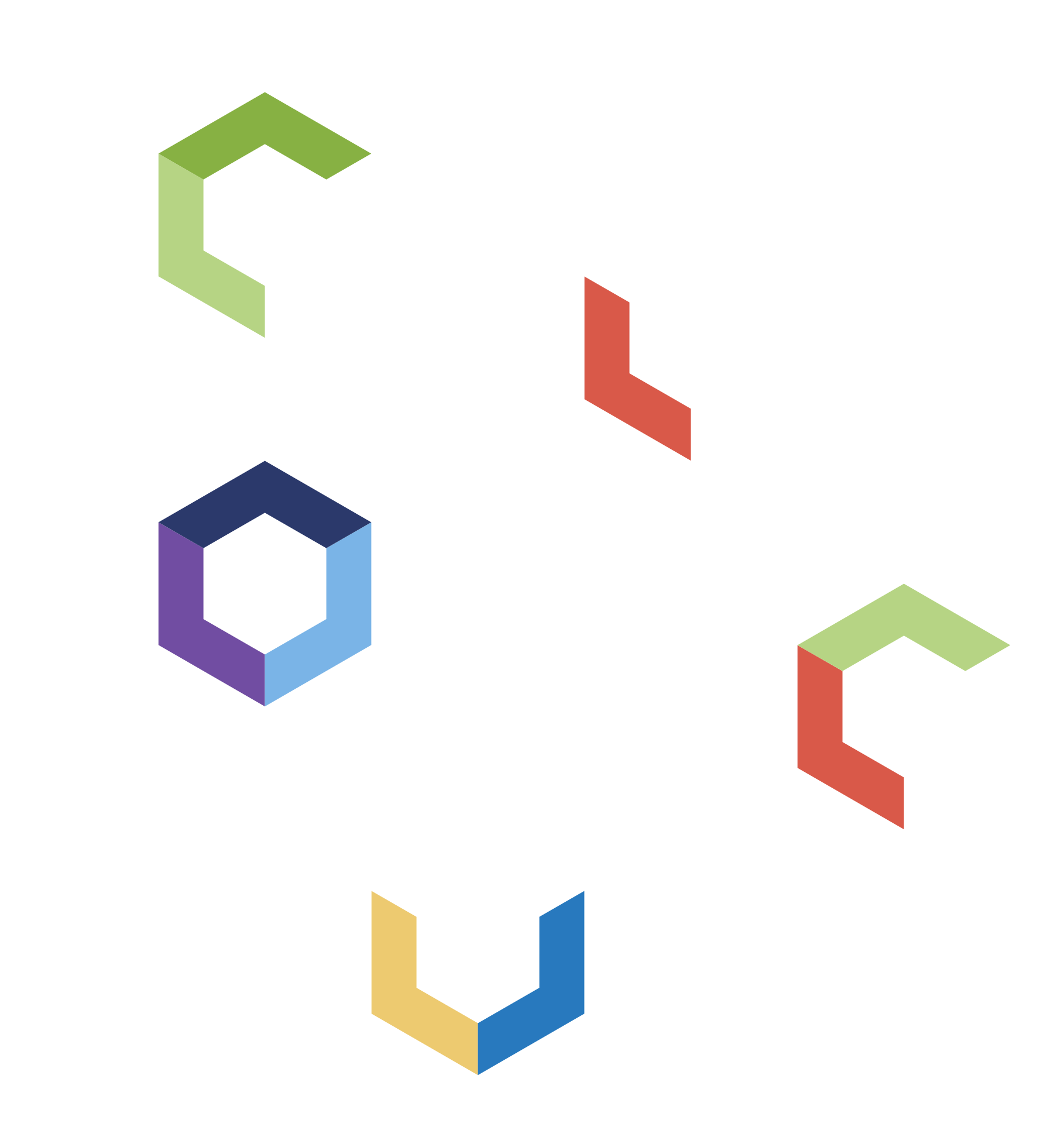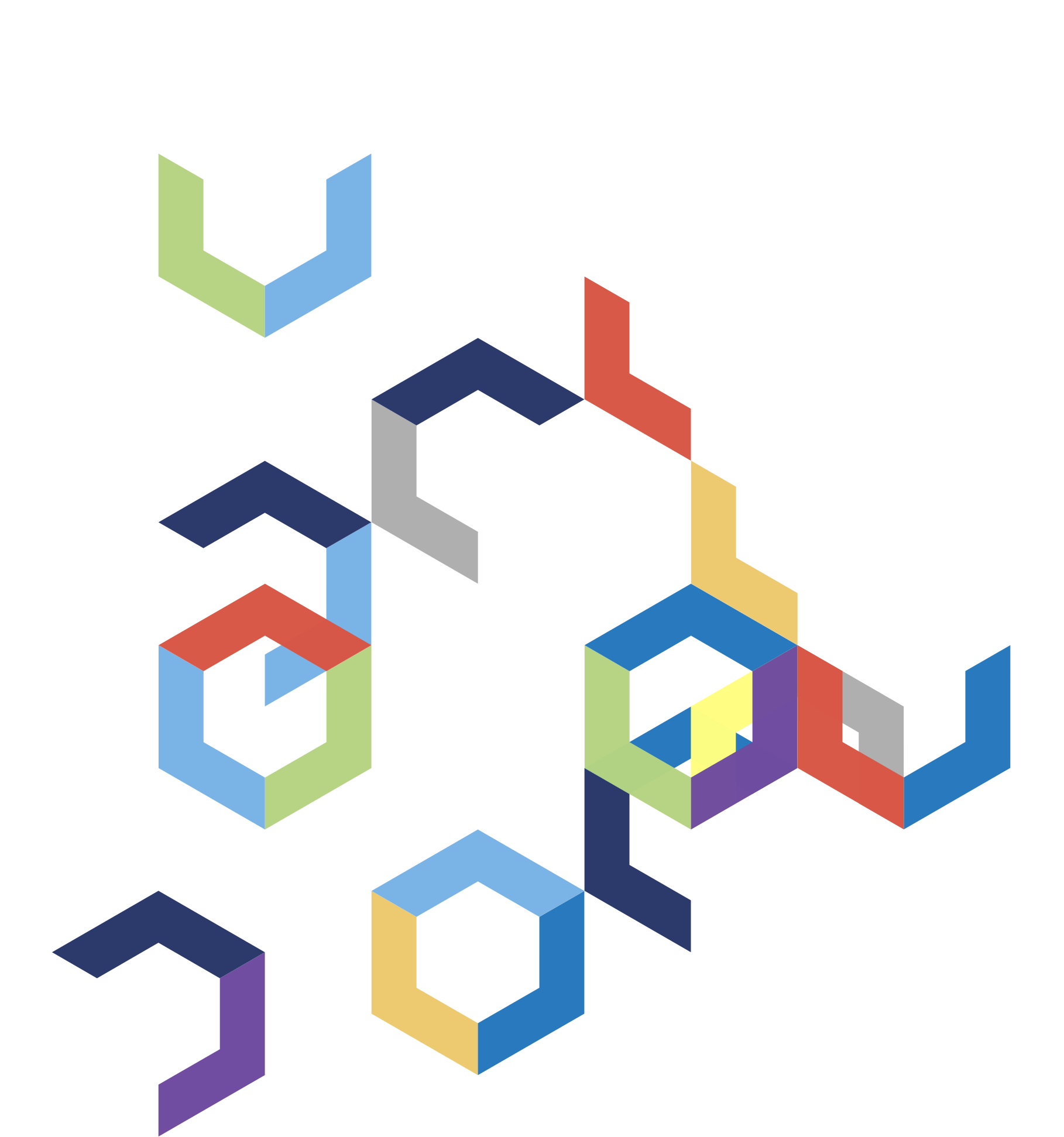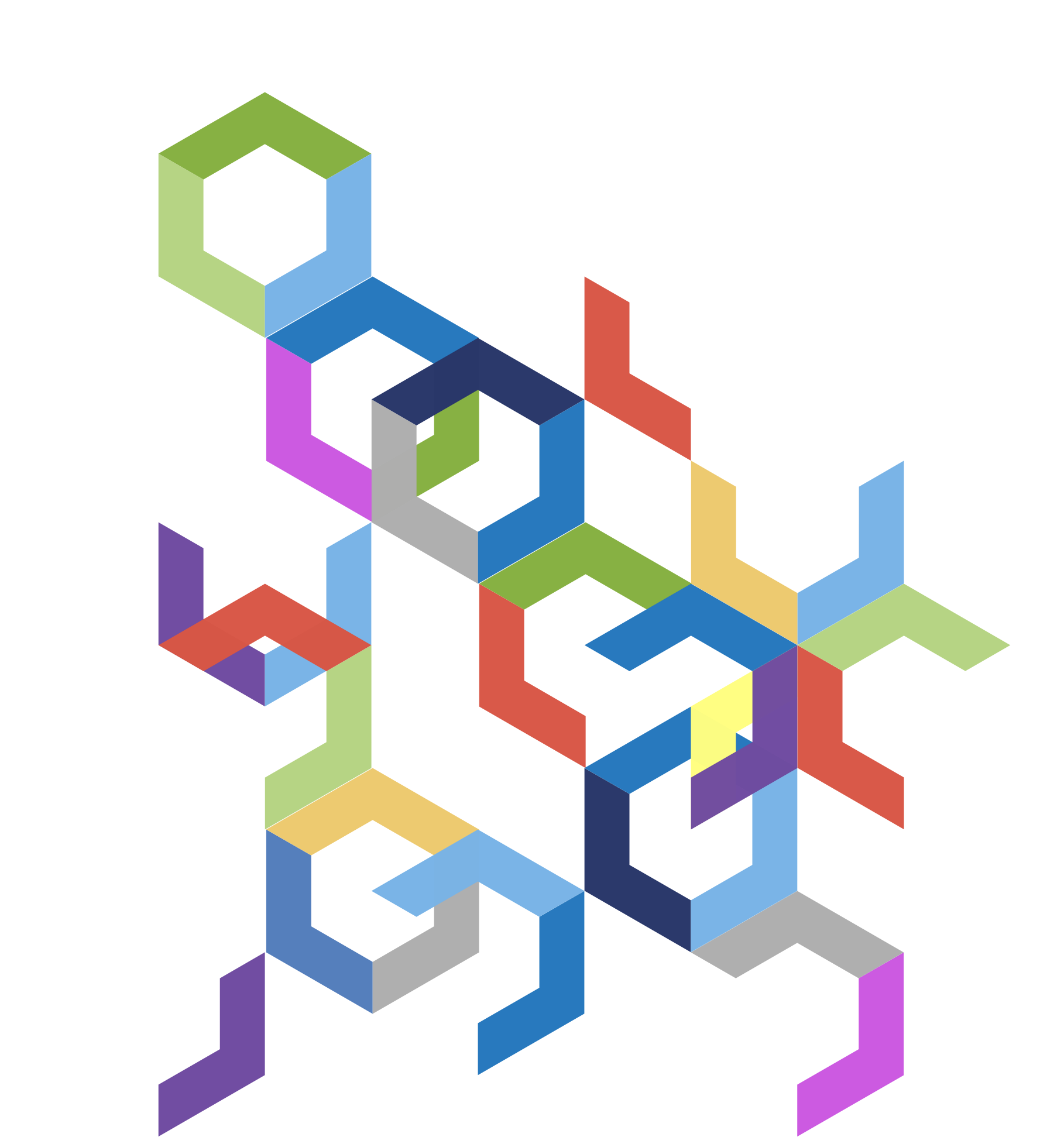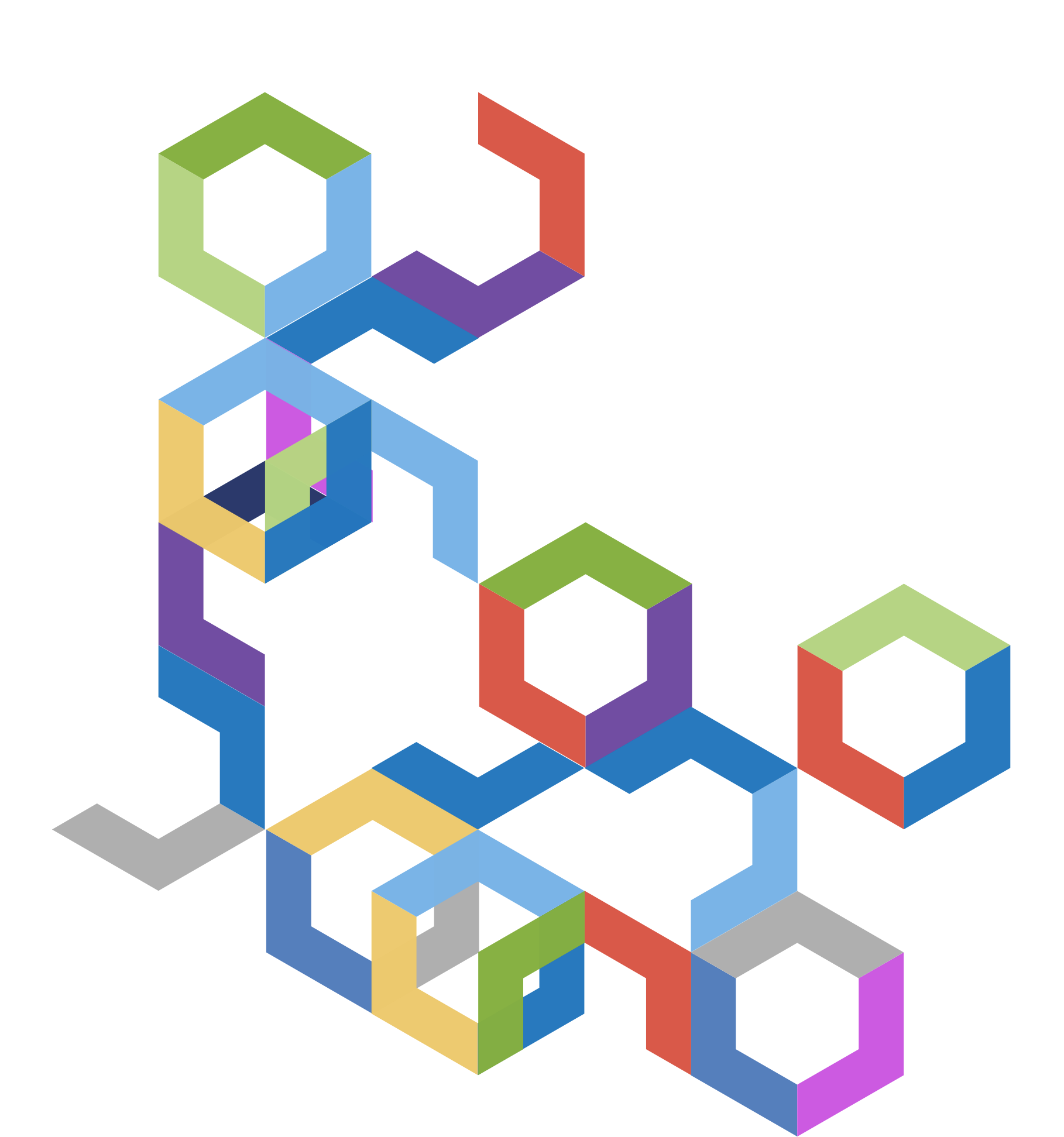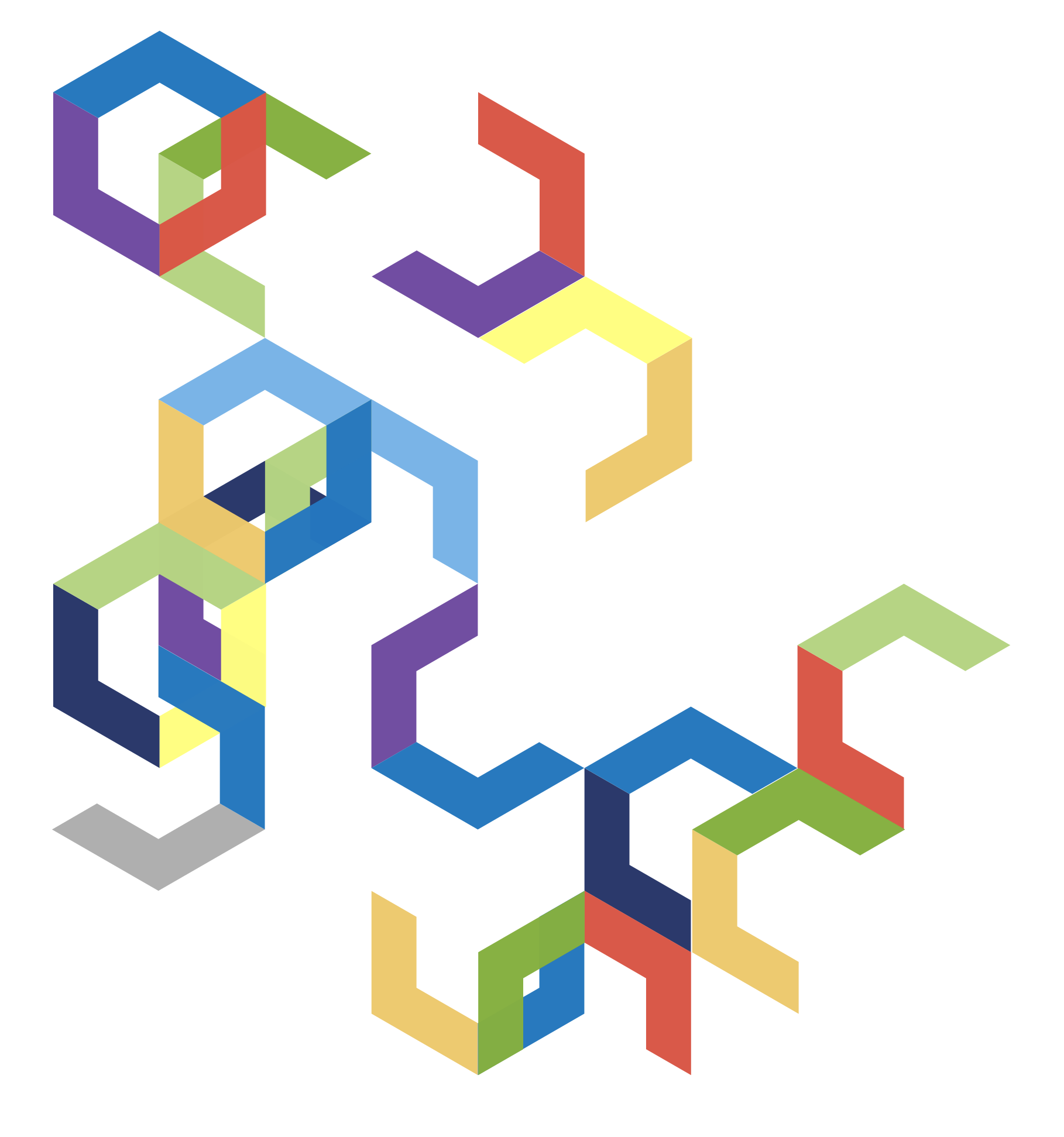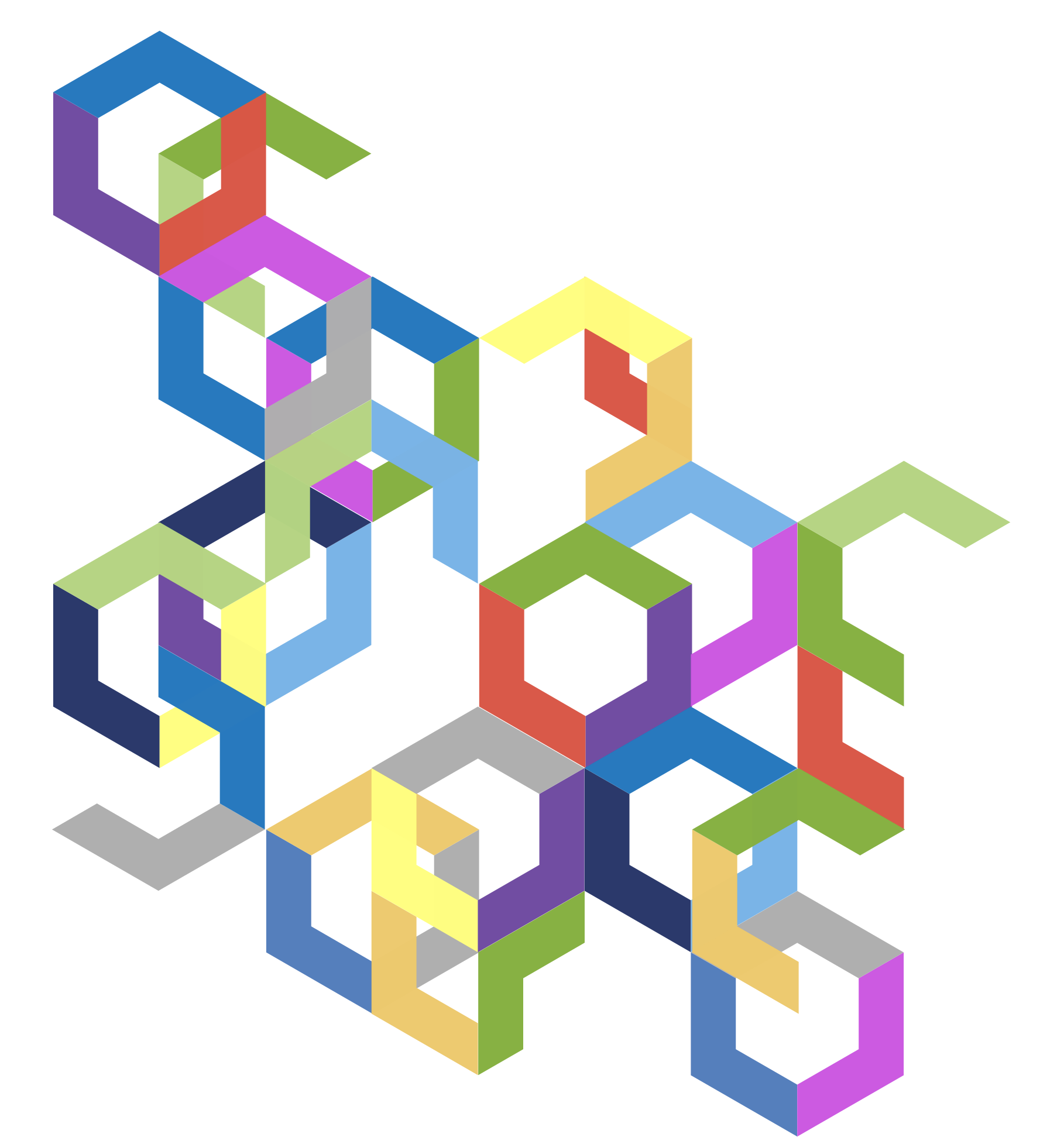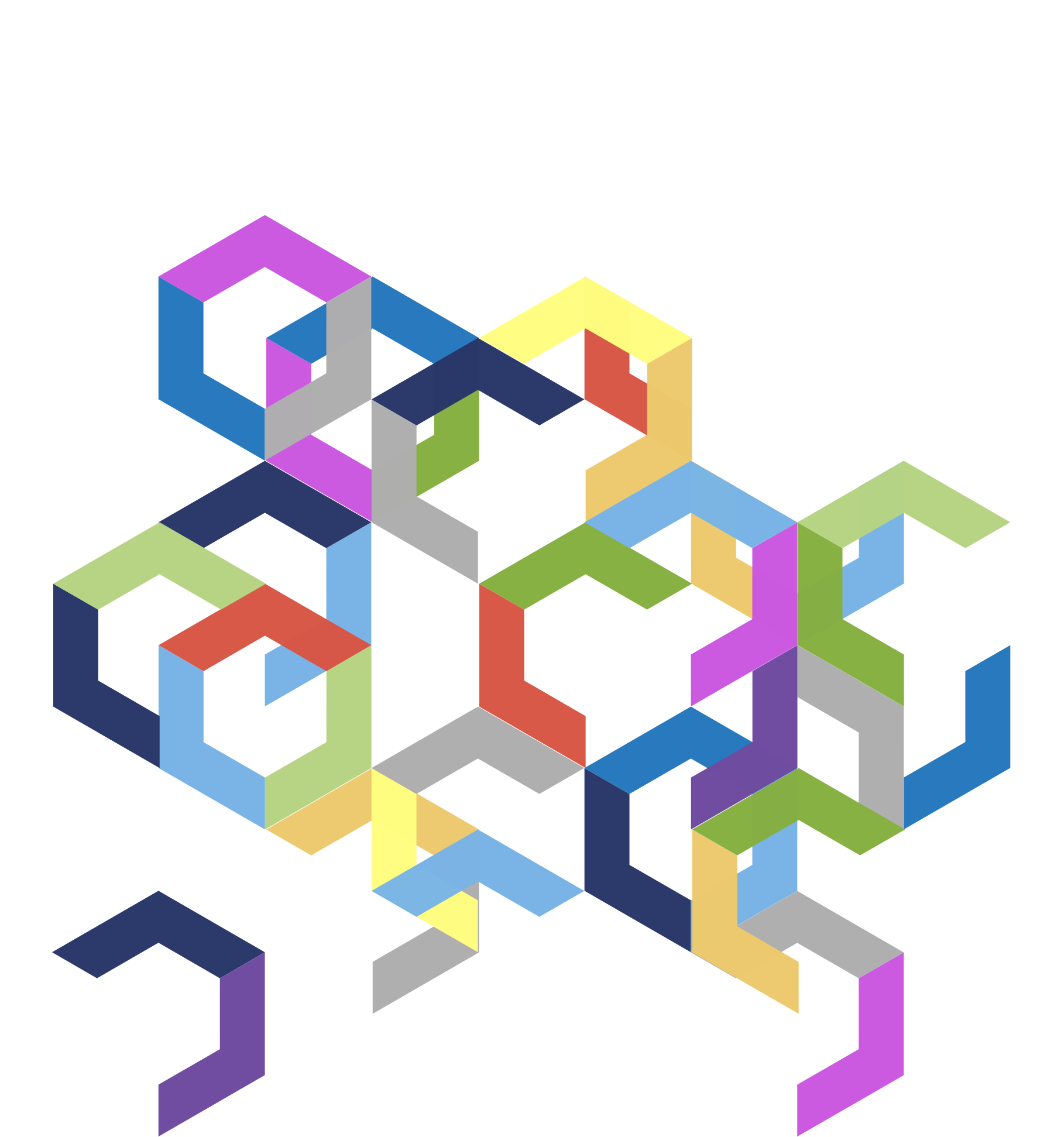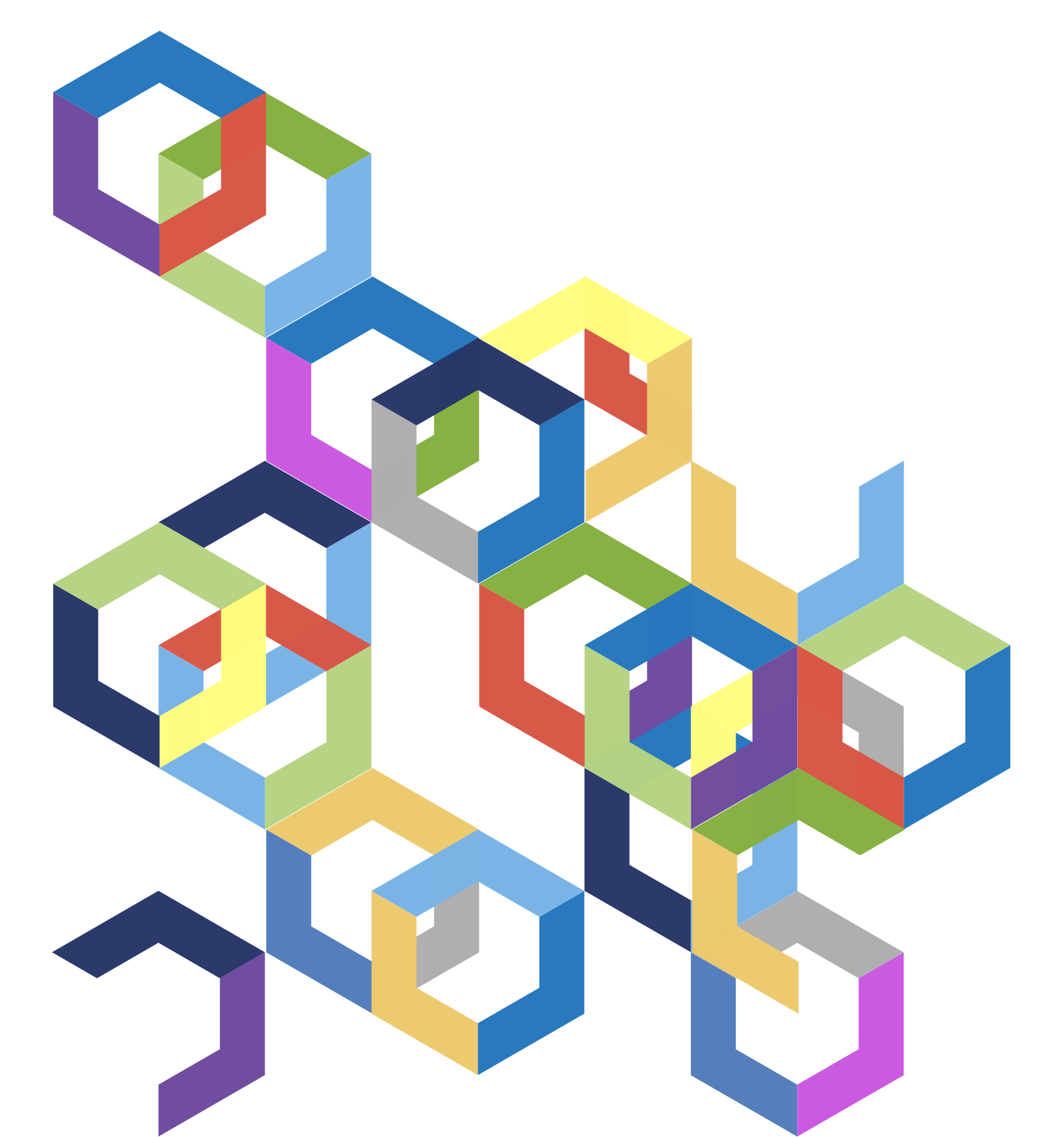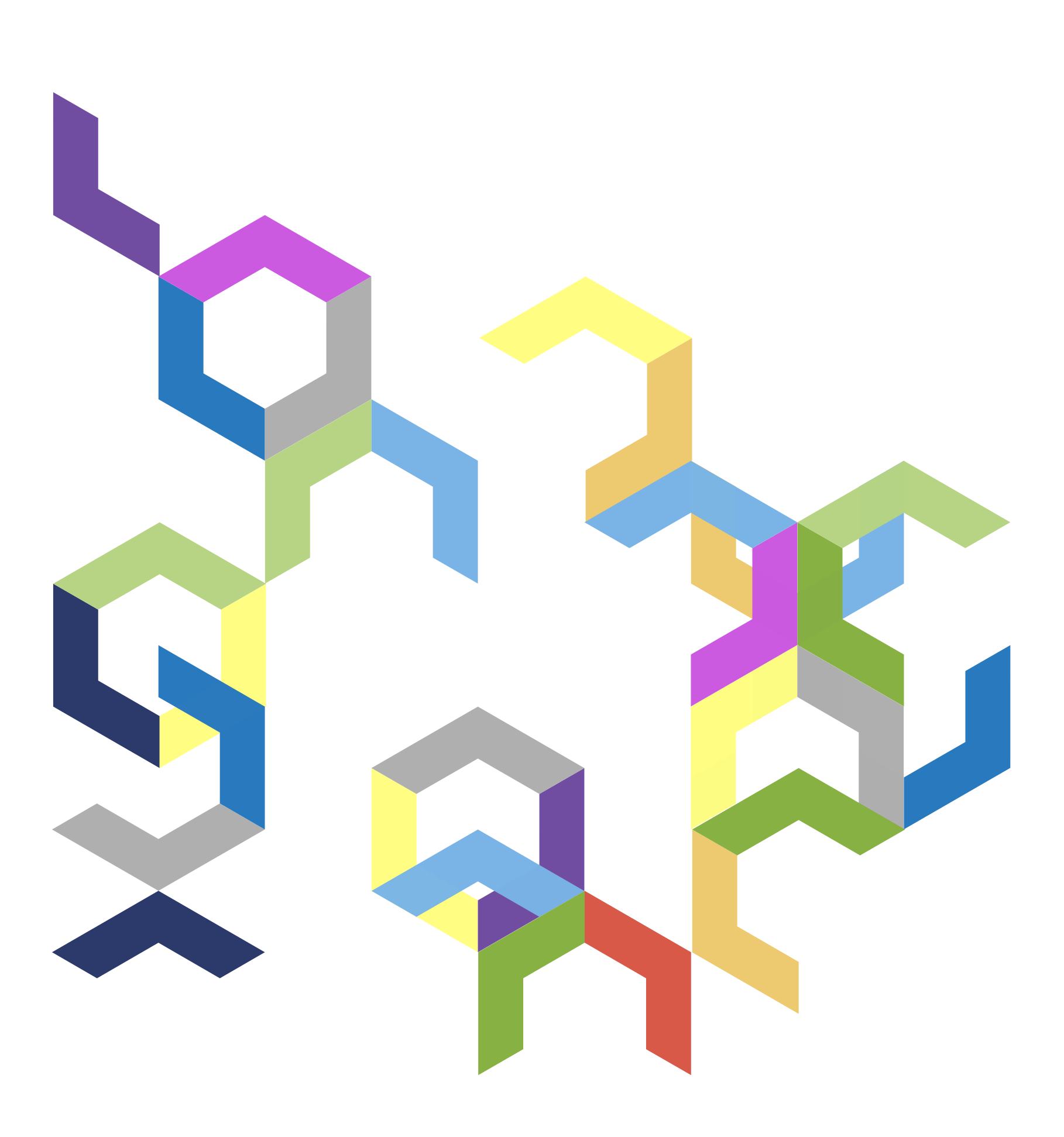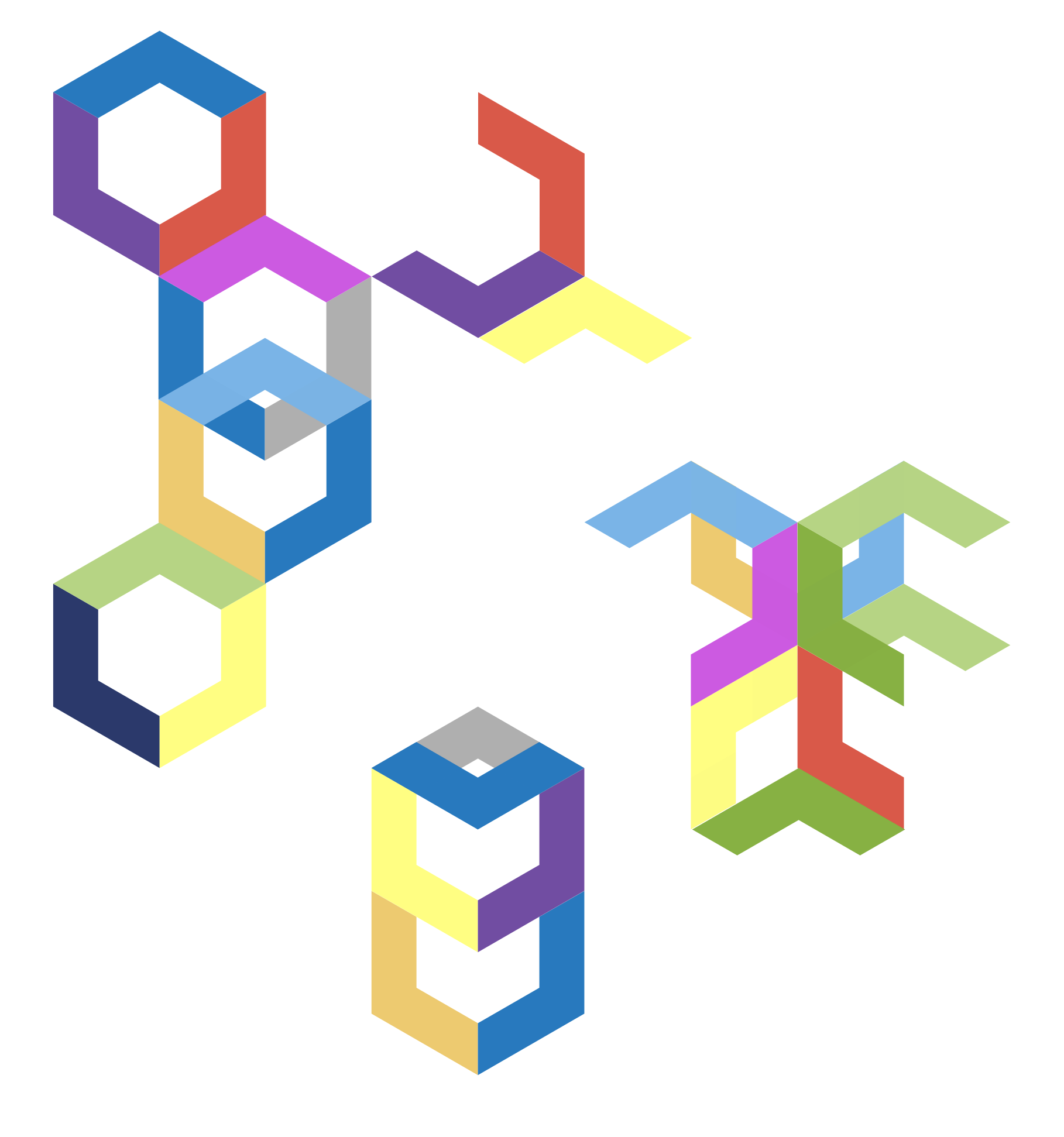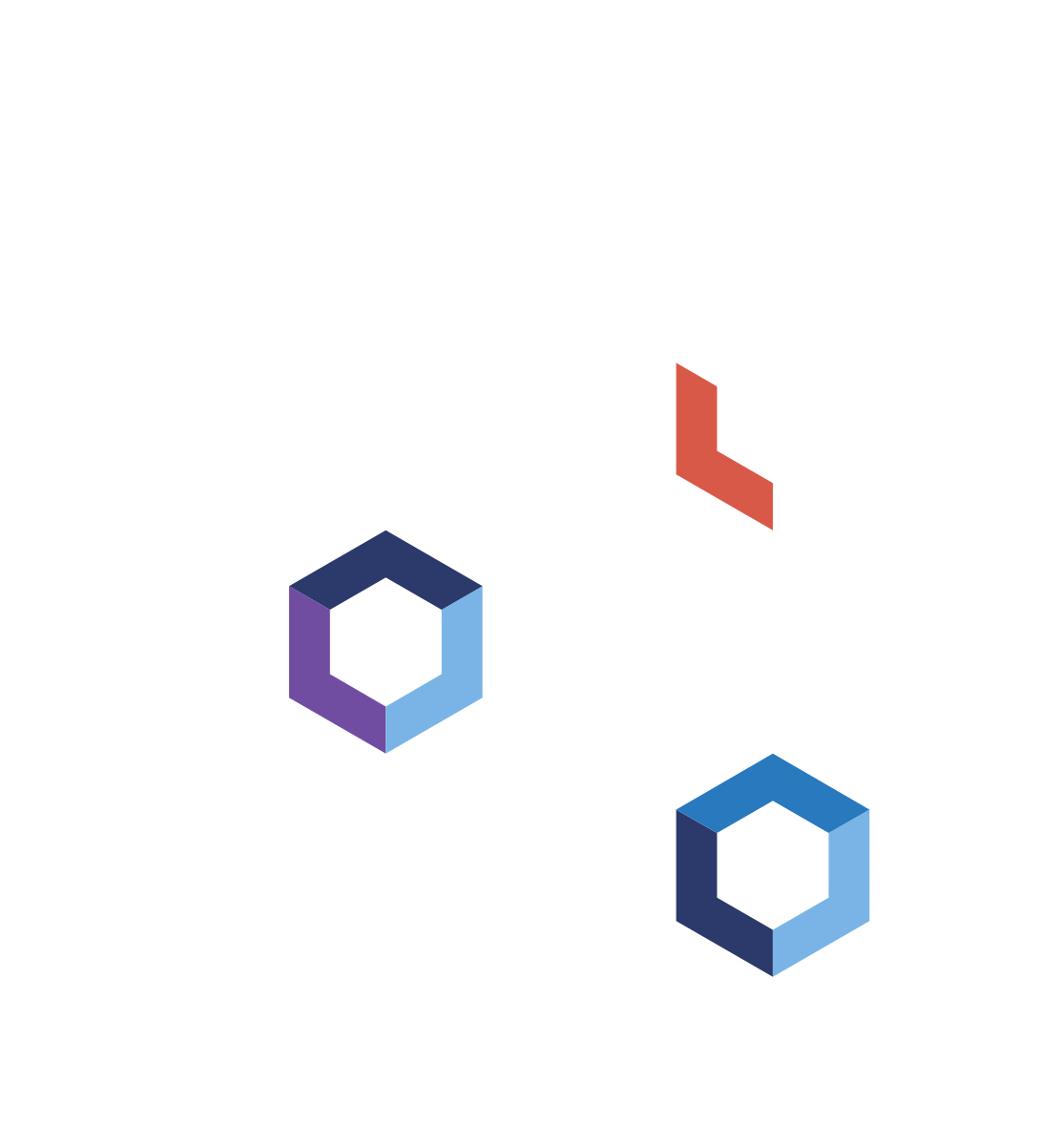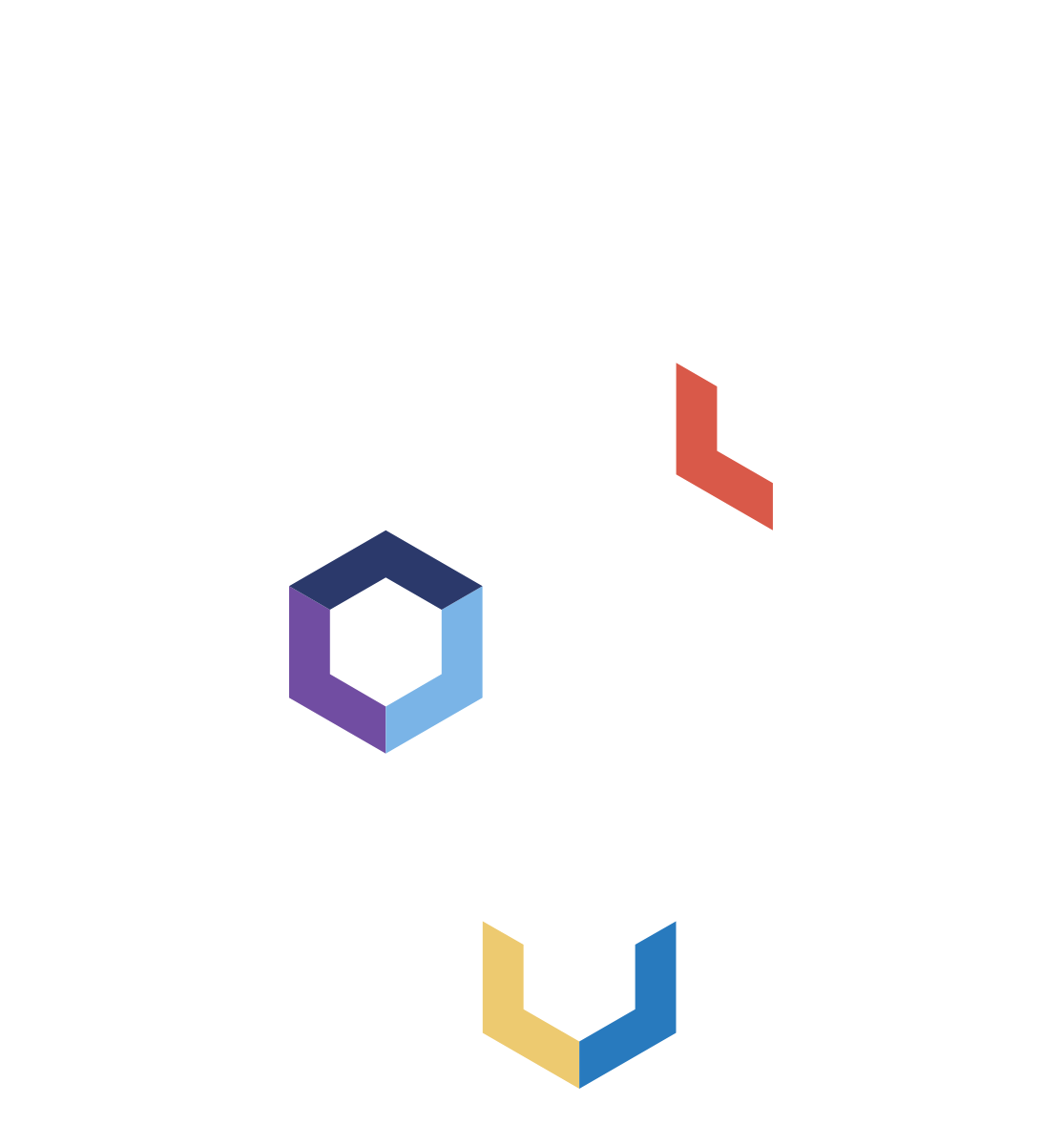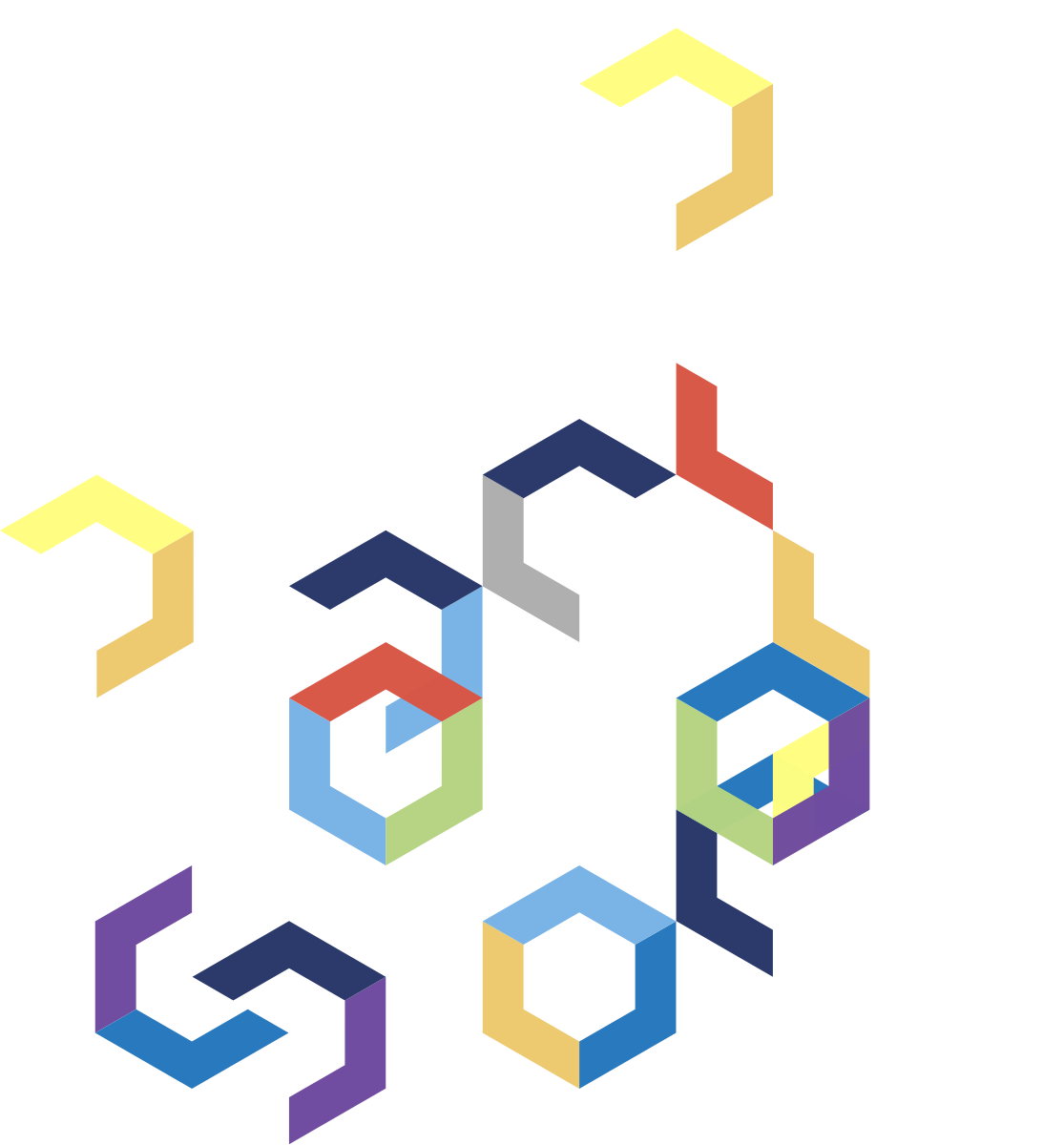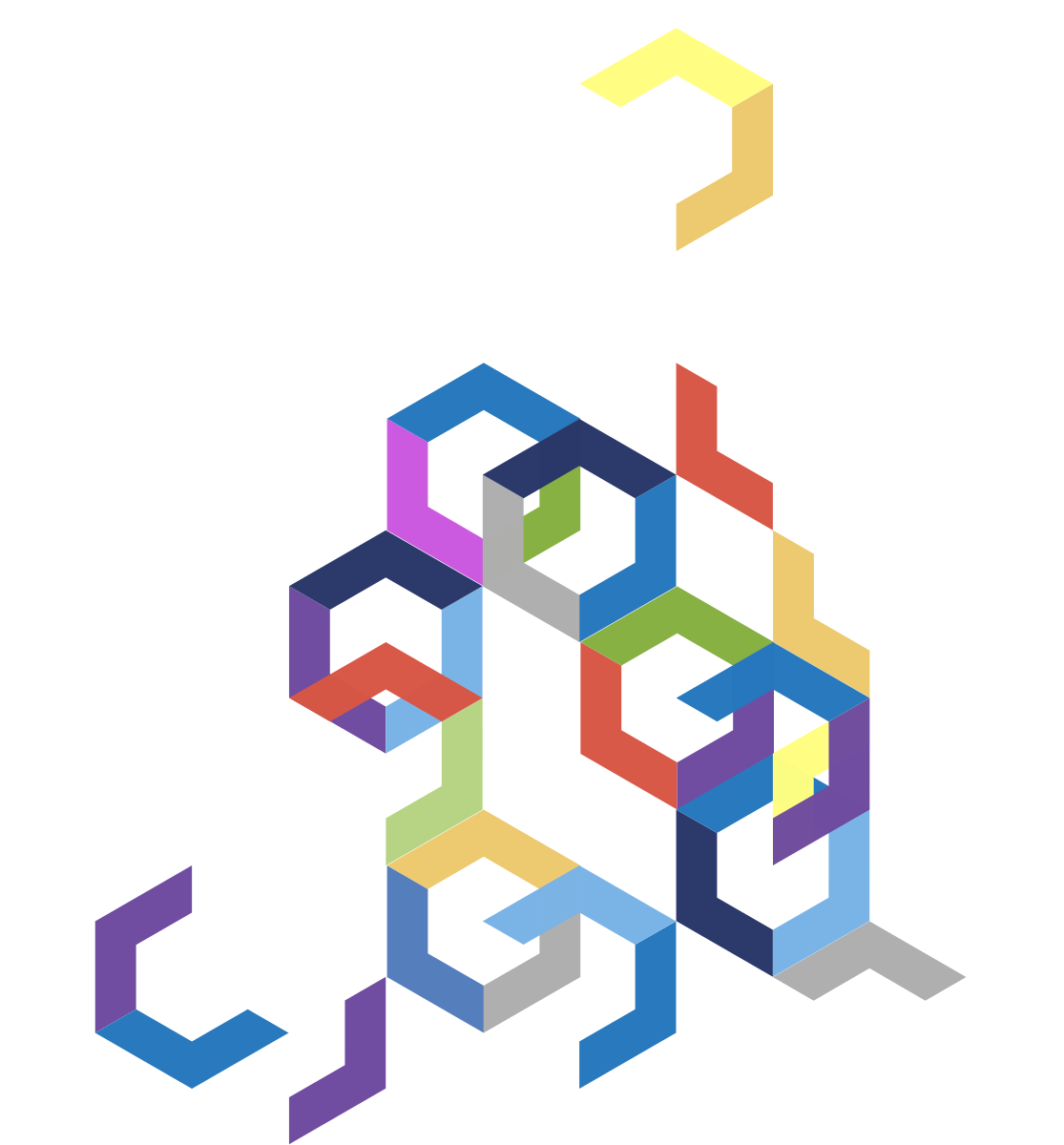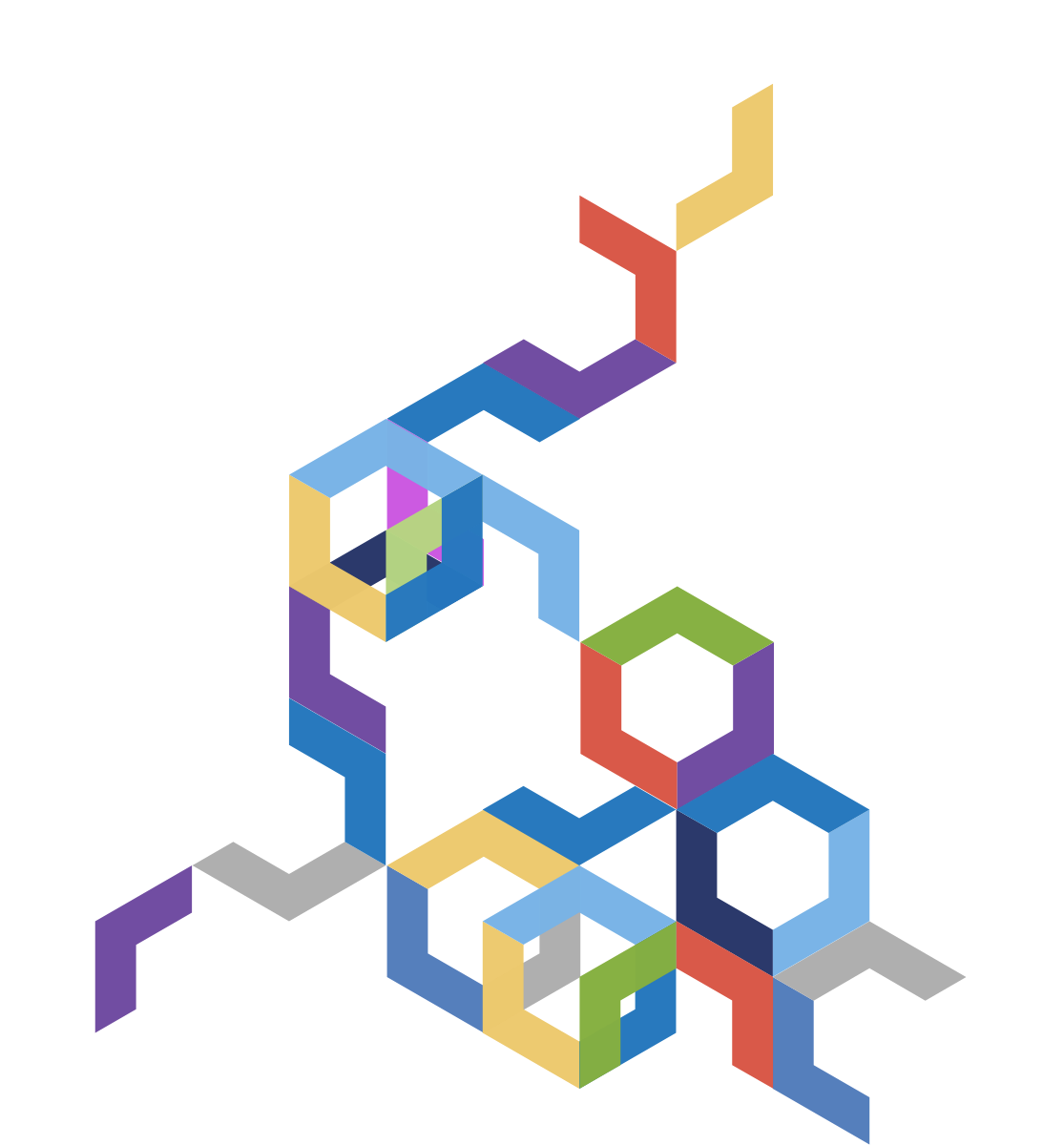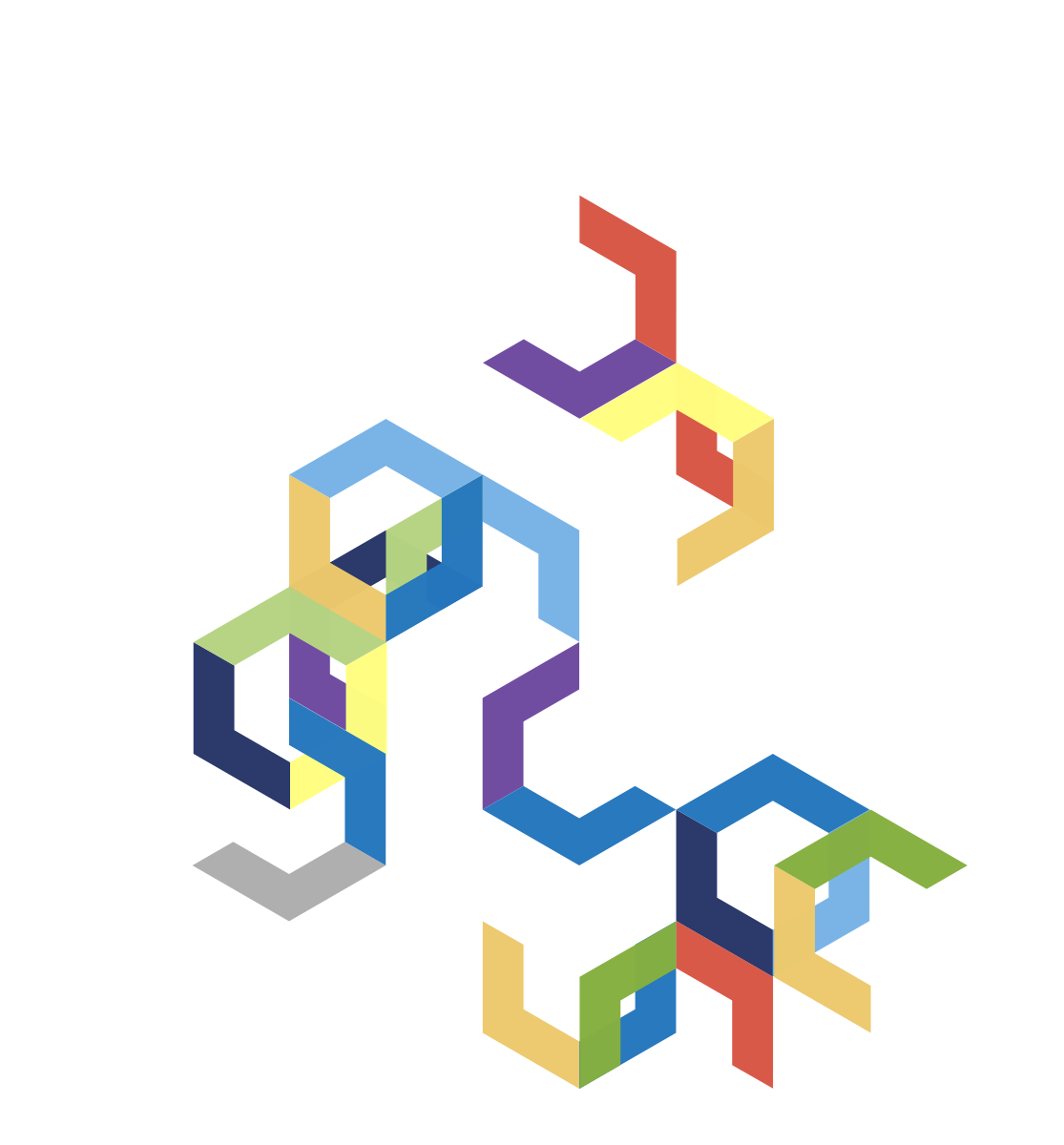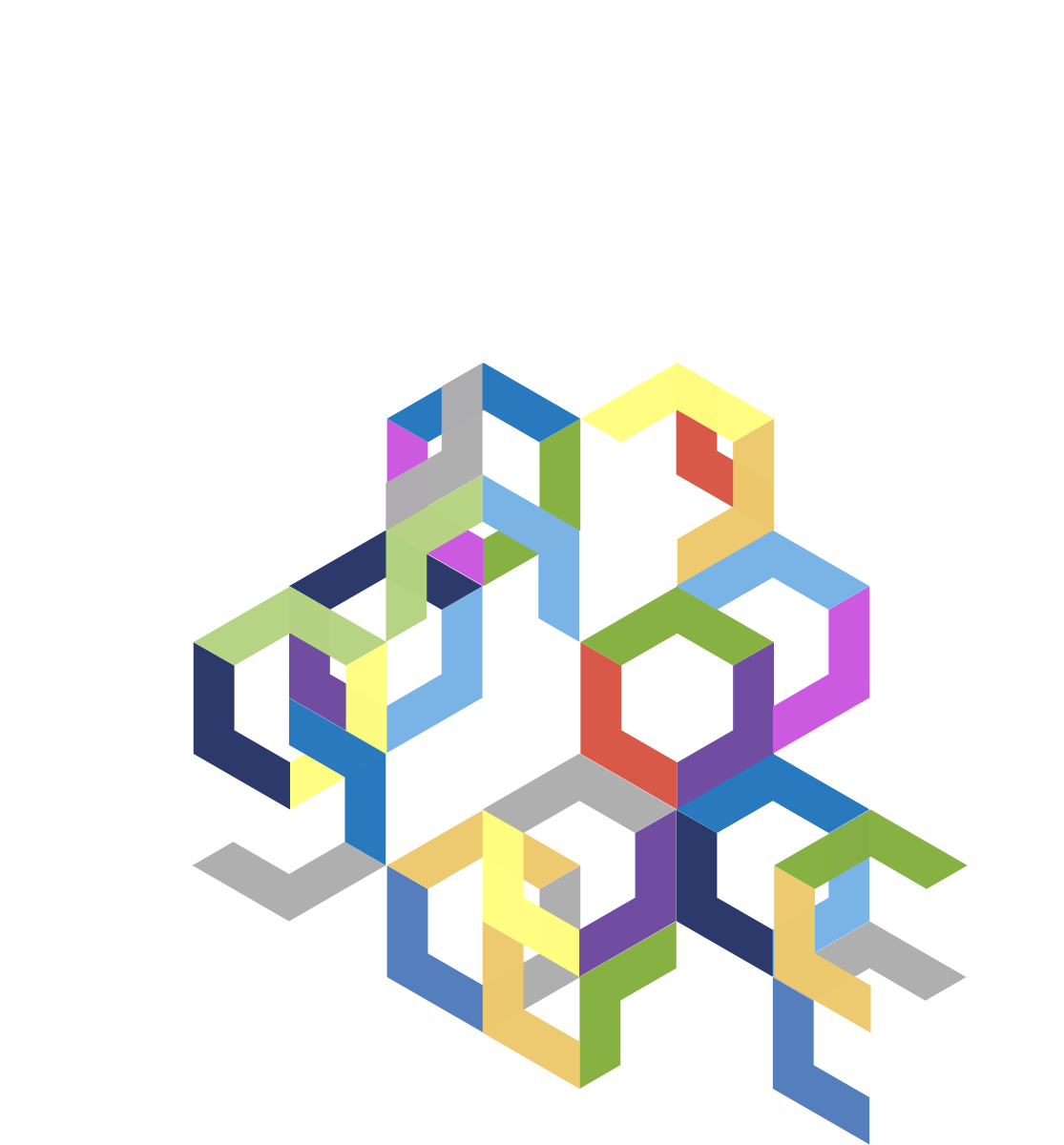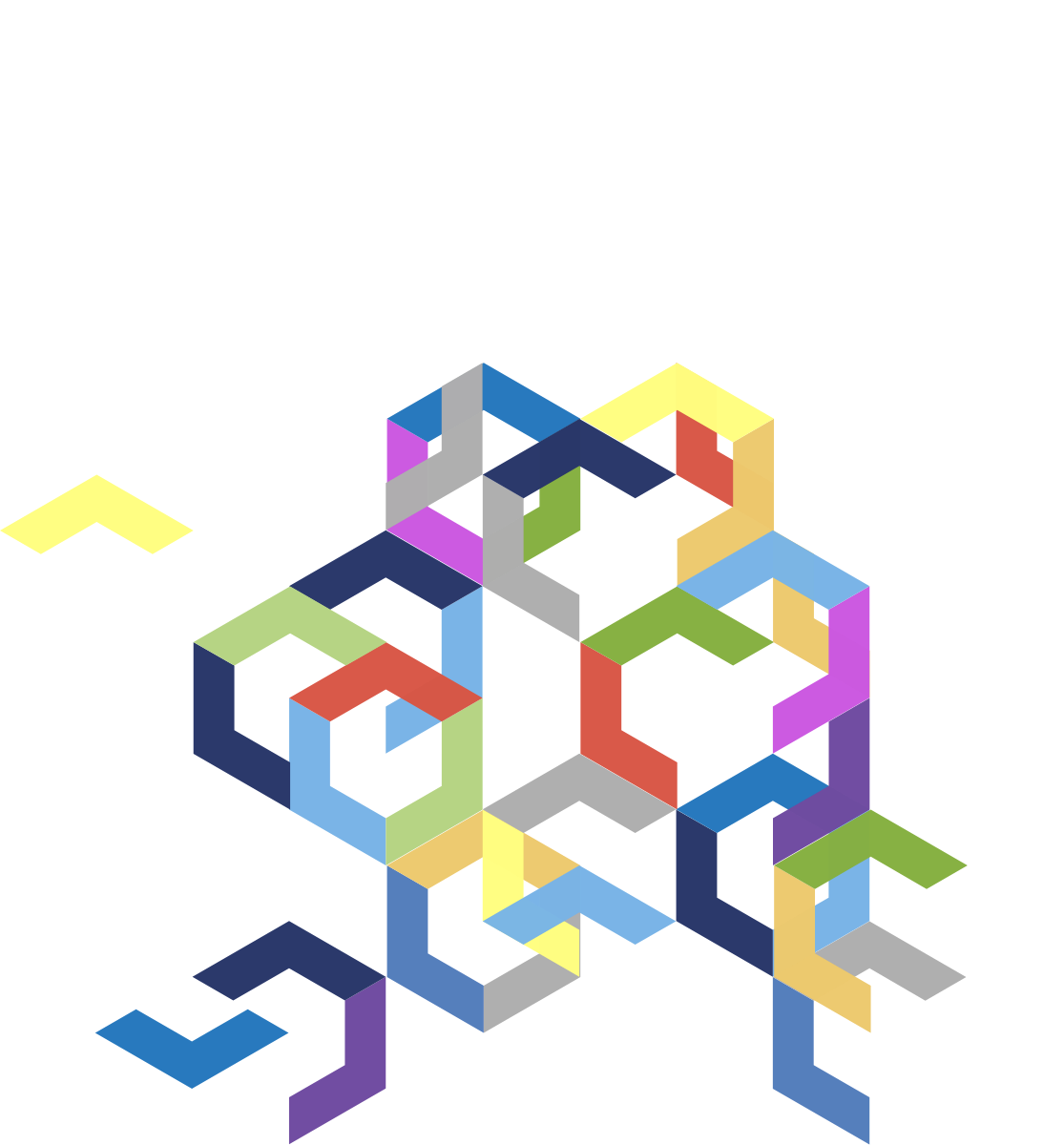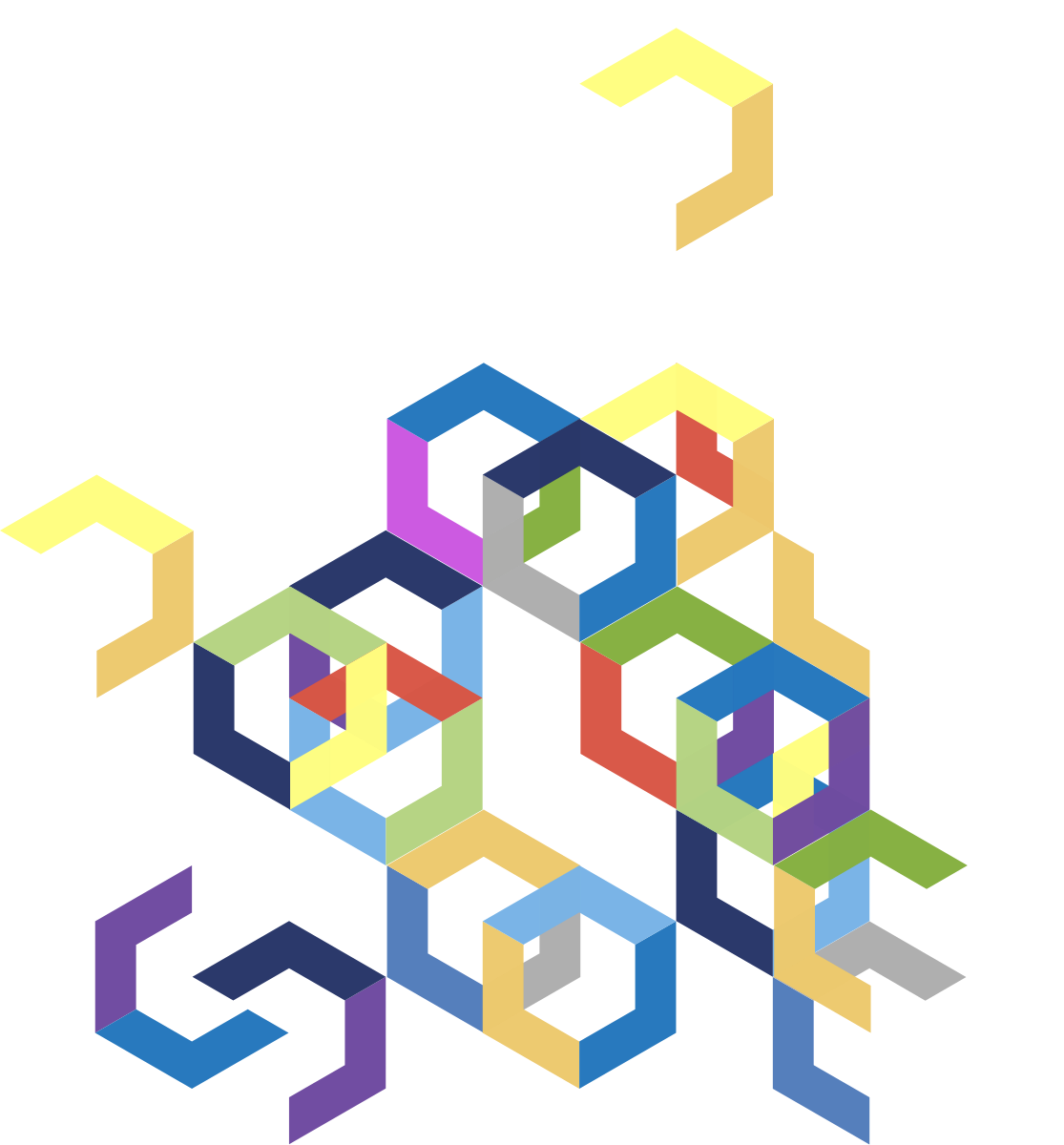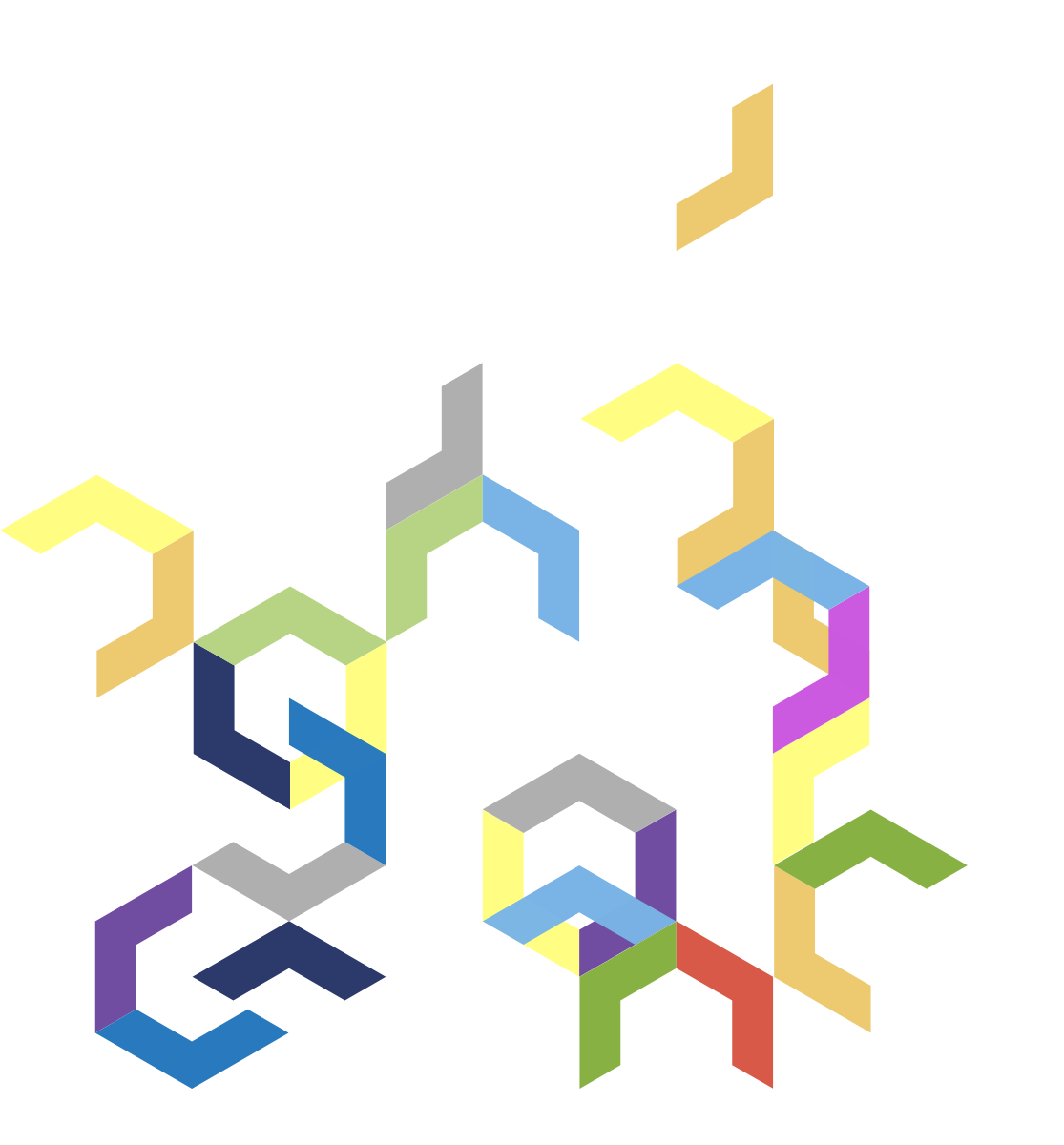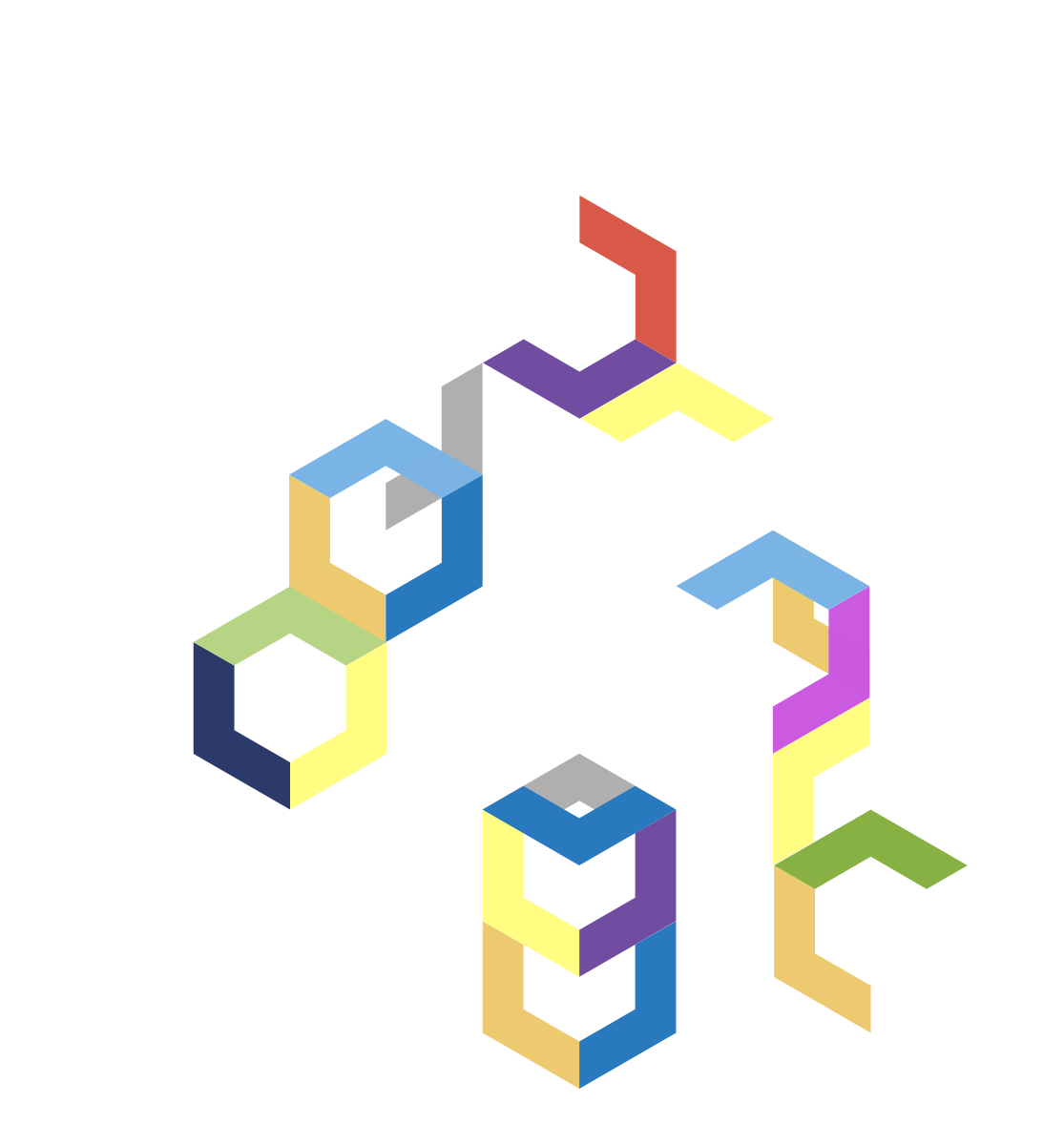ICT機器で「Want=〜したい」を叶える支援〜首から下が自由に動かない生徒への支援実践報告〜vol.3 表出と結び編✨
2025.10.31
研究・報告この実践報告の内容は今回でラストになります!vol.3 表出と結び編です!
3 メールという「つながり」の扉をひらく
メールが使えるようになったことも、今回の支援を通して得られた大きな成果のひとつです。
これまでは、早退やお迎えの際、学校側が保護者へ電話をかけ、保護者が迎えにくるという他者を介したやりとりが当たり前の光景でした。しかし今では、本人が自分でメールを使って、保護者に状況を伝え、依頼することができるようになっています。
こうしたやりとりは、学校だけにとどまりません。休日に一人で留守番をしているとき、たとえばトイレで困った場面でも、自ら保護者にメールを送り、冷静に状況を伝える力が育ってきました。
これは単なる技術の習得ではなく、「自分の気持ちや困りごとを、他者に言葉で伝えられるようになった」という、大きな変化です。さらに今回、本人にとって非常に大きな出来事がありました。それは、“家族以外の大人に、自分の悩みを初めて相談できたこと”です。D&Iセンターで活動する障害当事者である高野先生に、学校生活で感じているモヤモヤを、自分の言葉でメールに綴って伝えることができました。
これまで、相談といえば家族の中で完結していた彼にとって、「誰かに聞いてもらえる安心感」「言葉にして届けてみる勇気」は、まさに新たな“つながり”の扉を開く第一歩となったのです。
4 自分の意思を言葉にして伝える 〜「合理的配慮」について考えるきっかけ〜
定期テストのふりかえり音声メモのなかで、本人ははじめて「合理的配慮」に対する自身の思いを言葉にして伝えてくれました。
「漢字の問題をなくしてほしいんです」これは、これまで一度も自分から訴えたことのなかった願いでした。たとえば、歴史や理科など“内容理解”を測るはずの設問で「漢字で書けたか」が採点の決め手になると、漢字の想起や運筆といった別の要素(構成概念)が点数を左右し、学習内容の理解や日々の努力と切り離された評価になりかねません。この発言は一見すると「できないからやめてほしい」という要望にも聞こえますが、私たちは「学習内容の理解が適切に伝わる別の示し方はないか」という提案として受け止めました。本人も、評価の焦点を漢字の正確さ“だけ”に置くのではなく、理解を示す手段(読みの説明、口頭での要素提示と代筆、適切な選択肢形式、タイピング等)を一緒に考えたいという趣旨を言葉にし始めたのです。
この申し出を受けて、私たちD&Iセンターは、単に“なくす”という対応ではなく、「どうすれば“本人の理解を適切に評価する方法”になるか」を一緒に検討することを提案しました。支援とは、本人の願いを尊重しながらも、評価の目的に合ったよりよい学びの仕組みへとつなげること。本人自身がその一歩を踏み出したことに、大きな意味があると感じました。
学校側からも「これまで通り、連想できる構成要素を口頭で伝え、それを代筆する方法でよいか」「もしくは選択肢の中から選ぶ形に変更した方がよいか」と、具体的な代替方法について相談がありました。学習の目的をふまえつつ、「どの方法が本人の力を最も正確に伝えられるか」を、丁寧に話し合っています。「本人が自分の思いを伝えることそのものが学びである」という視点が、今回のやりとりに表れていました。
D&Iセンターとしては、今後も、本人・学校・家庭がともに対話を重ねながら、状況に応じた柔軟な合理的配慮の在り方を共に模索していきたいと考えています。「支援される側」から「支援を提案する側」へと、一歩踏み出したこの経験が、今後の本人の学びと自立の大きな礎になることを願っています。
✨おわりに:「〜したい」を大切にするということ
この実践を通して、私たちが改めて感じたのは、「〜したい」という気持ちの持つ、力強さです。
たとえば、好きな動画を探すこと、振り返りをスライドにまとめること、自分の言葉で思いを綴ること。それらはどれも、勉強やリハビリのように「何かのために頑張ること」とは少し違って、“やってみたいからやってみる”という、ごく自然な行動のかたちでした。けれど、そこにこそ、本人の意欲が生まれ、成長につながる土壌がありました。自分の興味から始まり、自分で選び、自分で表現してみる。そうして「できた!」という実感をひとつずつ積み重ねるたびに、本人の表情や言葉に、少しずつ変化が見られるようになっていきました。操作のしやすさや、声で動かせるという特性以上に、ICTは「自分の力で何かができた」という実感をともなった経験の扉を開いてくれました。
もちろん、すべての場面で万能なわけではありませんし、支援が不要になったわけでもありません。むしろ、本人の「〜したい」という気持ちが芽生えたからこそ、周囲の関わりも「やらせる支援」から「ともに考え、見守る支援」へと変わっていく——そんな相互作用が、今回の実践にはあったのだと感じています。
日々の学校生活の中で、私たちはつい「できる・できない」という基準で子どもを見てしまいがちです。けれど、「何ができるか」ではなく、「何をやってみたいか」から始める関わり方こそが、子ども自身の可能性をひらくきっかけになるのではないでしょうか。
ICTは、そのための道具にすぎません。けれど、「〜したい」と願った気持ちを尊重し、それを実現できる環境が整ったとき、子どもたちはきっと、自らの力で歩みはじめます。
私たちはこれからも、「できるかどうか」ではなく、「やってみたいと思えるかどうか」という視点を大切にしながら、子どもたちと共に新たな一歩を踏み出していきたいと思います。
ICT機器で『Want=〜したい』を叶える支援とは、まさにその一歩を可能にするための、優しく力強いサポートだったのです。
最後までお読みいただき、ありがとうございましたm(__)m